
2011年3月28日(月)
しばらく中断していましたが、本日より再開します。
これまでの経過
前回まで28回にわたって、CO2温暖化論の基礎である世界気温について、IPCCや、世界の気温データを管理してきたNOAA、CRU、NASAが公表してきたデータに関して、いろいろな角度から検証された結果を紹介してきました。
そして、IPCCの主張の根幹である「20世紀後半において、大気中CO2濃度が増大した結果、地上気温が急激に(かつてないほど)上昇した」とする言い分に関しては、世界の気温データからは確かな根拠が見出せないことを、順を追って説明してきました。
しかしながら、友人・知人と話していると、基本的な部分で誤解があるように思えることから、今日は、繰り返しになりますが補足説明しておきます。
CO2温暖化論は、以下の論理で構築されていました。
1)20世紀後半に、人類の排出したCO2が大気中に蓄積して濃度がかつてないほどの高水準になった。
2)地球温度は、20世紀後半にかつてないほど異常に上昇した。
3)だから、20世紀後半の地球温度上昇は、CO2の影響に違いない。
4)このままCO2排出が続けば、21世紀には更に温度が上昇し、人類に不幸な結果をもたらす。だから、直ちにCO2排出を削減しなければならない。
こうした理屈は、上記2)が事実であること が前提でした。
●20世紀において地球気温は確かに上昇したのでは、という意見
CO2温暖化論に異議を唱えることに対して、“でも、我々の環境は確実に温暖化しているのでないか”という意見が結構あるようです。本ブログではその点は論理的に説明してきた積りですが、再度、触れておきます。
地球気温は、平均的には20世紀において確かに上昇したでしょう。それは、18世紀後半から世界のいろいろな地点で氷河が後退してきた事実で、十分、証明されていると思います。重要なことは、大気中CO2の増大が始まった1950年頃よりもずっと前から、地球は温暖化していたという点です。即ち、地球の長期的な温暖化傾向とCO2の話とは、基本的には無関係であるということです。
但し、20世紀後半においても長期的温暖化は継続していた可能性があります。しかしながら、IPCCの主張は、20世紀後半の世界気温上昇はほとんどがCO2の影響だったという立場であり、長期的温暖化の影響は無視しています。この点については、赤祖父氏のような意見があることを紹介しています。(NO24,25)
●20世紀後半に、我々の住環境では実際に気温は大きく上昇したのでは、という意見。
この点について、本ブログでは、三つのことを、繰り返して述べてきました。
(1)都市温暖化にかかる気温上昇の問題
多くの人々は都市に住み、世界の全ての都市で20世紀後半に急速な都市化による気温上昇(都市温暖化)がありました。大抵の気温観測点は都市およびその近傍にあり、温度計の表示(読み)は上がったのです。人々の感覚は間違っていないのです。
しかしながら、IPCCは、自ら発表してきた気温データでは、都市化による要因は除かれている、都市化の影響は無視できるほど小さかった と主張してきたのでした。
ならばそれが本当だったのか、という視点が重要になります。そして、本ブログでは、IPCCデータでは都市化要因は除かれていないし、むしろ、かなりの部分は都市温暖化そのものだったというのが、結論だったことを紹介しました。(NO21など)
米国では、クライメートゲート事件後に各種メディアがいろいろな情報を伝えてきたことで、かつては米国人の多くが何でもCO2の所為と思ってきたのに、昨今では、近年の気温上昇は都市温暖化であることを冷静に理解している、と伝えられています。
一方、日本のメディアは、上述のIPCCの主張についても、気温データの実態についても、国民に対して正確な情報をほとんど伝えてきませんでした。その結果、多くの日本人は、都市温暖化とCO2温暖化の話が区別されていないようです。
(2)世界気温データにおかしな操作がされていた可能性が高いということ。
IPCCが公表してきた気温データに関して、CO2温暖化論に懐疑的な多くの人達から、データは意図的におかしな操作がされているという指摘がされてきました。クライメートゲート事件後は、そんな疑惑への追及が激しくなり気温データを管理してきた当局も情報開示をせざるを得なくなりました。
その結果、世界各地の気温元データに変な補正がなされていたこと、1200kmルールという勝手な理屈にもとづいてとんでもないデータ処理が実行されていたこと、など、様々な仰天事実が明らかになってきたのでした。(NO4〜NO7)
本ブログでは、こうした操作がされていない世界各地の生の気温データはどうだったのか紹介しIPCCデータと比較してきました。その結果は、「20世紀後半に地球温度が、かつてないほど異常に上昇した」というIPCCの言い分は、当局による気温データ操作の結果に過ぎなかったのでは?”ということでした。
大気中CO2濃度が急増した20世紀後半においても地球温度の異常な上昇があったとはいえない、ということになれば、CO2温暖化論の根拠は一気に崩れるし、将来のCO2の更なる増大による危険性の主張にも、大いなる疑問が生じたということです。
(3)北半球の高緯度地域の気温上昇が大きかったというのは、真実かという点。
IPCCは、20世紀後半の急速な気温上昇は、北半球の高緯度地域の上昇の影響が大だったとして、気温上昇の大部分は北半球の寄与であり、その75%は北の寒い地域の気温上昇だった、としていました。
具体的には、20世紀において、北緯60度以北では平均で約3℃上昇し、北緯20度から60度までが約1.5℃上昇、北緯20度以南では0.5℃上昇した、といった数字を挙げてきました。そして、北の寒い地域は21世紀において更に大きく上昇すると警告してきました。この点はCO2温暖化論の正当性を主張する根幹部分でした。
従って、本ブログでは、“寒い所は気温があがりやすい”は“ほんとうだったか”という視点で世界各地の寒い地域の気温データを見てきました。(NO8〜NO14)
その結果、寒い地域の生の気温データ(当局の操作前のデータ)は、IPCC主張とは大違いで、かなり広範囲な地域で、気温は上昇するどころか、低下していた可能性が高く、全ての寒い地域で、20世紀後半に気温が急上昇した所は存在しなかったようなのです。
IPCCデータは、1200kmルールを適用して、北の寒い地域の生データの代わりに、南の方の都市化によって表示気温が上がった地点データを適用していたという、とんでもない証拠も、いろいろと紹介してきました。
●大気中CO2濃度が増えているのだから地球温度が上がるのは当然では、という意見。
CO2温暖化論はCO2が温室効果を有することを出発点にしているわけで、こうした素朴な疑問が出るのも当然かも知れません。この点について本ブログでは、CO2濃度増加が気温に与える影響について、理論ではどうなっているのか紹介しました。(NO15)
CO2温暖化論では、CO2濃度の増加自体による気温上昇が主要因ではなく、水蒸気ポジティブフィードバック効果が働くという仮説が理論の骨格であることを紹介しました。更に、水蒸気ポジティブフィードバック効果は、寒い地域でより効果を発揮するとされていました。“寒い所は気温があがりやすい”というIPCCの言い分は正しいかったのか、が焦点だったのでした。
しかしながら、寒い地域のほんとうのデータは、IPCCの言い分とは大違いでした。この理論は“ウソだった”と断定できるほどに事実は違っていたのです。上述のIPCCの論理の内、3)20世紀後半の地球温度上昇はCO2の影響に違いない、という理屈が否定されたということです。
●でも、将来はどうなるか判らないのでは、という意見
IPCCの言い分は、このままCO2排出が続けば21世紀には更に温度が上昇し、人類に不幸な結果をもたらす。だから、直ちにCO2排出を削減しなければならない、でした。
そして、そうした警告の根拠として、気候モデルにもとづいたコンピュータシミュレーションの結果を持ち出しました。
IPCCの2001年第三次報告書の中で、以下の図1のような21世紀の気温予測図が掲載されました。2000年以降における経済発展モデルをいくつか想定して、人為的CO2排出量推移を予測し、コンピュータシミュレーションによって、地球気温がどう変わるかを予測したのです。四つのモデルが示されています。気温は、概略、直線的に上昇すると予測されていました。
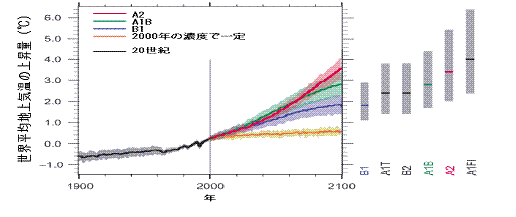
図1 IPCCによる気候変動(気温変化)の将来予測 |
2000年の時点からの21世紀末における気温上昇は、3.6℃(赤色)〜1.8℃(青色)と解析されました。なお、橙色は、2000年時点でCO2排出増加を止めたとする、現実的にあり得ないケースでした。
では21世紀も10年が経過した今日、実際はどうだったかというと、IPCCのデータにもとづく世界平均気温は、あり得ないケースの橙色の線以下で推移しています。
更に、ブログで指摘してきたように、いろいろな指標が少なくとも今後の数十年間は気温低下を示唆しています。
上記のIPCCの論理の4)このままCO2排出が続けば21世紀には更に温度が上昇し、人類に不幸な結果をもたらす、は明らかに間違いだったとデータは示しているのでした。
●IPCCの報告書は、世界中の科学者が議論した結果で間違いないのでは、との意見
“IPCCの結論は世界の2500人の科学者の総意である”という話は、世の中に知れ渡りました。しかしながら、クライメートゲート事件が明らかにしたことは、科学者の総意どころか、IPCCリーダー科学者達による醜悪極まる行為でした。そして彼らは、自分たちの思想を死守するために、世界気温データにかかる情報を独占している立場を利用して、気温データまで怪しげな操作をし、一部データは消去してしまったのでした。
CO2温暖化論を推進してきた政治家、官僚、IPCCのリーダー達にとっては、“IPCCの結論は世界の2500人の科学者の総意である”は、CO2温暖化論が科学論としてまっとうであることを強弁する手段だった、のかもしれません。いま、米国、英国などCO2温暖化論を推進してきたお膝元でも、科学者達の間でCO2温暖化論があまりにも非科学的であること、IPCCという組織のひどさに、批判の声が高まっています。
終わりに、ブログWUWTの2010年12月5日に掲載されていた米国漫画家JOSHという人によるCO2温暖化論の風刺絵を示します。
温室効果(GreenHouseEffect)、化石燃料(FossilFuel)CO2、CO2レベル増加、CO2の重大性という四つの足を持つ机の上に、Chicken Little(評判だおれという意味か)の気候警告モデル、決してこぼれない(No Spill)コンセンサス紅茶(“2500人の科学者の総意”を皮肉った)、100%DataFreeの研究ビスケット(おそらく、研究者が気温データを自在にいじっているという皮肉)が載っています。
CO2レベル増加の足はLogarithmicという本に乗っていてCO2による温室効果が対数で効くので増加しても気温が上がらないことを表現し(推測)、化石燃料はNatural Variationという本にのっていて、地球上の膨大なCO2の自然循環が適切に評価されていないことを意味すると思われます。CO2の重大性の足はWater Vapourという厚い本で底上げされ、これは水蒸気フィードバック仮説を皮肉っています。 まことに秀作です。
|
2011年3月3日(木)
“地球気温変化の本当の原因は何だったのか”の観点から、海洋および大気の振動現象の紹介をしています。今回は、太平洋10年規模振動(Pacific Decadal Oscillation:PDO)を説明します。
太平洋10年規模振動(Pacific Decadal Oscillation:PDO)は、1997年に発見されました。これは、太平洋の各地で、海水温や気圧の平均的状態が10年を単位として2単位周期で変動する現象です。図1に指数の推移を示します。
指数がプラスの時(赤)は、北東太平洋で南風が強くなり地球全体が温暖な気温となり、一方、マイナスの時(青)は気温が低下する、とされてきました。
20世紀においては、地球気温が大きく変化した時期が三回あったとされていました。
1920年から1940年頃の温暖化時期
1950年から1975年頃の寒冷化時期
1980年から2000年頃の温暖化時期
PDO指数は、この三つの時期で明瞭に変化していて、気温の変化とよく対応しているのが特徴です。
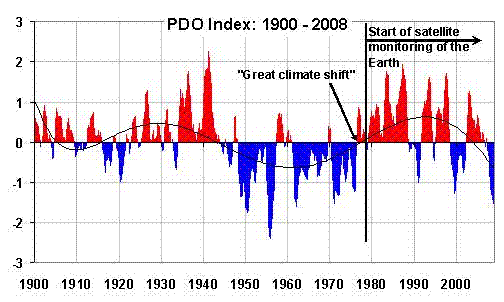
図1 PDO指数の推移 |
但し、PDO自体が独立して発生する現象であるとは確認されておらず、いろいろな現象が複合して現れた結果という見方もあるようです。
これまで説明してきたように、地球全体の正確な気温データがあったわけでありませんでした。また、IPCCの発表資料や、NOAA、NASA,CRUなどの気温データ管理組織が公表してきた数字にはおかしな補正がされていました。
世界平均気温なるものの実態は、地球気温推移の真の姿であったとは思えない状況です。しかし少なくとも、北半球に位置し、海洋の影響が大きい北米、北欧、アラスカ等では、NOAA、NASA,CRUなどによるおかしな補正がされていない生の気温推移は、明らかに、PDO指数の変化と実に良く対応していました。
上図から判るように、2000年以降は、PDO指数がマイナス指数の時期に入っています。これは、すくなくとも、北半球の海洋周辺の気候は、今後の20年から30年間は、寒冷化時期となることを暗示しています。
エルニーニョとラニーニャの推移、北極振動指数、PDO指数のいずれもが、今後の寒冷化を示しています。そして21世紀に入ってから、大気温度は既に上昇がとまり、海面温度は低下の傾向を示しています。地球全体として寒冷化に向かっているように思えます。
“20世紀の後半の気温上昇のほとんどが、CO2の増加による影響である”などと断定して、21世紀の異常な気温上昇を“予言”してきたIPCCやCO2温暖化論者の言い分が、如何に根拠のないものであったか、あらためて指摘されるべきでしょう。
地球気候の今後の推移については、おそらく誰も確定的なことは言えないのでしょう。寒冷化するにしても、1950年から1975年頃のレベルに止まるならば、大きな被害は起きないでしょうが、14世紀頃から18世紀にかけて経験したような小氷河期のような寒い時期にまで進むとしたら、人類にとっては大変なことになるでしょう。
人類は、温暖化への対策でなく、寒冷化への対応を準備するべきなのです。
|
2011年2月28日(月)
地球気温変化の本当の原因は何だったのかの観点から、海洋および大気の振動現象の紹介をしています。前回はエルニーニョとラニーニャについて説明しました。
今回は、北極振動(Arctic Oscillation:AO)について説明します。
北極振動は、1998年に見出された現象で、北極の低気圧が周期的に強弱を繰り返す現象のことです。エルニーニョとラニーニャの場合と同様に、気圧変化における係数変化(AO指数と呼ぶ)で表わします。平年より低気圧が低いときはプラス指数、逆の場合はマイナス指数になります。
ウィキペディアに記載されている北極振動指数の変化を図1に示します。
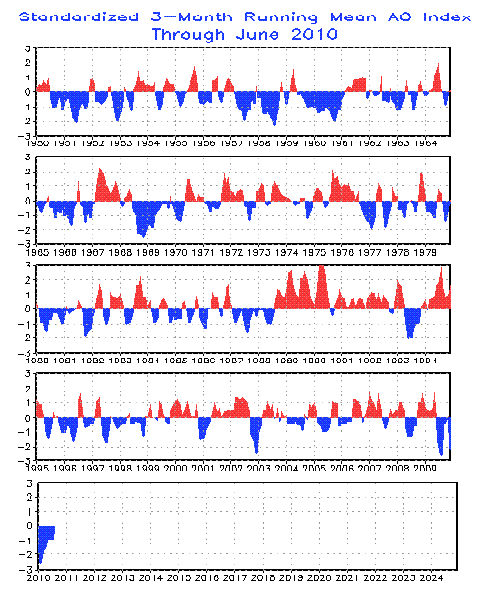
図1 北極振動指数の推移(赤がプラス、青がマイナス) |
北極振動の影響は冬季に顕著に現れます。北極低気圧が平年より低い(AO指数がプラス)時は、北に向かう南の暖かい風が強くなり、北半球の気温は暖かくなります。
気圧が平年より高い(AO指数がマイナス)時は、この逆の変化が起きます。
北極振動が発生する原因はよくわかっていないようですが、太陽活動の変化との関連を指摘する研究もあります。
上図からわかるように、指数は短期間(1年〜3年程度)でプラスとマイナスを行き来していますが、どちらかが優越する期間が数十年単位で変化することもあります。
1950年代〜1970年代はマイナス指数が優越していた時期で、地球気温、特に、北半球の気温低下と相関が見られます。前回にも書きましたが、この頃は氷河時代が到来すると騒がれていたのでした。
1980年代以降はプラス指数が優越し、北欧、北米、アラスカ、カナダ、ロシアなどを温暖化させた、とされています。
北極振動は、北太平洋や北大西洋からの北極海への海流の流入に影響を与えることによって、北極海氷の増減に大きな影響を与えていることがわかってきました。そして、「指数プラスが優越していた20世紀後半において、南の暖かい海水の北極への流入が増加して北極海氷を減少させていた」とする説は有力になっているようです。
IPCCは、北極振動のように海流・大気に大きな変化を与える振動現象について十分な理解がされていなかった頃から、CO2が20世紀後半において地上気温をかつてないほどに上昇させたとし、このままCO2増加が続くと21世紀の前半までに大幅な気候変動を起こす可能性がある、と結論してきました。そして、アル・ゴア氏など温暖化論者達は、20世紀の後半における北極海氷の減少は、CO2増大による地球温暖化の証拠である、として誇大に報じてきたのでした。
2009年以降、AO指数はマイナス指数優越の傾向が出始めている、という指摘がされています。そして、2009年以降において、欧州、北米では冬季寒波が顕著になっていて、北極振動変化の影響が具体的な形で現れています。
エルニーニョとラニーニャの指数変化と同様に、AO指数もまた、寒冷化時代到来を暗示しているのかも知れません。
日本のメディア報道において、こうした寒波について、CO2増加による地球温暖化の影響だと示唆する論調もありましたが間違いといえるでしょう。 |
2011年2月21日(月)
前2回において、地球気温変化の本当の原因は何だったのか、の観点から、小氷河期と20世紀の関連について、赤祖父俊一氏の意見を紹介しました。
今日から、海洋および大気の振動現象について紹介してゆきます。
1987年に結成されたIPCCは、増加するCO2が地球気候に深刻な影響を与えると断じて、以降、CO2が諸悪の根源であるかのような主張が展開されました。そして、IPCCは、20世紀後半の気温上昇はCO2の影響だと断定しました。
しかしながら、地球気候に多大な影響を与えているとされる北極振動や太平洋振動(PDO)などが発見されたのは1990年代の後半でした。この一事をもってしても、IPCCの結論は、独断と独善に基づくものだったことを示しています。
地球気候は、海洋と大気の状況が周期的に変化することで大きく変動してきました。海洋や大気の変動(振動)は、1〜2年の短い時間で発生し収束することもあれば、数十年の周期で変化する場合もあります。従って、20世紀後半の、たかだか、20年程度のデータに基づいて、“増加するCO2が地球気温をかつてないほど上昇させた”などと結論するのは、短絡的判断だったのです。
海洋・大気の変動現象の発生原因は十分に解明されておらず、変動が地域気候に与える変化についてもよくわかっていないのが実情のようです。
個別の現象が他の現象を誘起したりいくつかの要素が複合したりすることや、地域の変化が遠隔地にまで波及してゆくテレコネクションと呼ばれる現象があることなどが、解明を難しくしている原因とされています。
今日は、海洋および大気の振動現象の第1回目として、エルニーニョとラニーニャという現象について説明します。この現象は、太平洋の赤道近辺において、東側と西側で海水温度が周期的に変動する現象で、東側(例えばペルー沖)で温度があがるのをエルニーニョ、その逆の場合をラニーニャと呼びます。
エルニーニョとラニーニャは、南半球で生じる海洋・大気の振動現象である南方振動(SO)と密接な関係があるとされ、これらを併せてENSOと呼ばれています。
海洋・大気の振動現象は、気温、気圧などの変化を示す理論的の係数に着目して、平均値からのズレを 指数 で表示します。指数は正になったり負になったりし地域気温はそれによって大きくかわります。
図1は、1950年以降でのエルニーニョとラニーニャについての指数変化です。
赤は指数がプラスでエルニーニョが活発な時、青は指数がマイナスでラニーニャが活発な時を意味します。
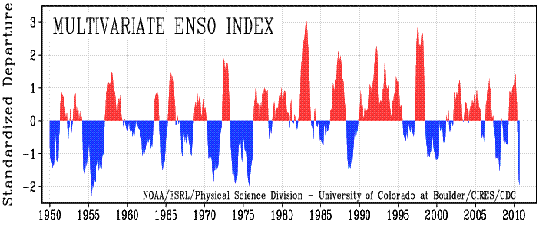
図1 エルニーニョとラニーニャの指数の変化 |
地球気候への影響の仕方は地域によって異なるようですが、一般的には、エルニーニョの時には地球全体で気温が上昇しやすく、ラニーニャはその逆となる傾向があるとされています。これは、太平洋の熱帯上での変化が、海流やテレコネクションによって、地球全体に影響を及ぼすということを示しているのでしょう。
なお、指数の大きさは影響の大きさとは比例しないようです。
図からわかるように、短期的な変化に加えて、数十年にわたって平均的にどちらかが優越する時期 があります。
1950年から1975年ぐらいまでは、ラニーニャが優越した時期でしたが、当時、地球気温は低下していました。ついでに言いますと、当時は、氷河時代が来ると大騒ぎされたのです。
一方、20世紀後半から21世紀初頭(1980年〜2005年)はエルニーニョが優越した時期で、気温は上昇しました。そして1980年代に入ってから、CO2増加の脅威が叫ばれ始めたのでした。
IPCCがCO2の影響だと大騒ぎした20世紀後半は、エルニーニョによる気温上昇が顕著な時期だったのです。そして、
21世紀になってから、再びラニーニャが優越する時期になったことが指摘されていて、今後、数十年は気温低下をもたらす可能性が高い情勢にあります。
エルニーニョとラニーニャについては、短期的な変化が気温に顕著な影響を与えることもあります。例えば、
1998年には、エルニーニョが地上気温および大気温度を大きく上昇させました。
CO2温暖化論者達は小躍りしてよろこんだことでしょう。
一方、2000年前後には、気温の低下や停滞が見られましたし、2008年は極端に寒い年となりました。これらはラニーニャの発生と相関が見られます。
なお、日本では何の報道もされていませんが、2008年には、大気中のCO2濃度増加は停滞していました。しかし人類のCO2排出量は当時も増加していたのです。
これは、大気中CO2濃度の増加が、少なくとも、単に排出量とだけ関係しているのではない可能性を示唆する、かなり重要な情報でした。
2009年から2010年の前半にかけては、再びエルニーニョが地上気温および大気温度を大きく上昇させました。そしてその後はラニーニャが優越してきました。
2010年の南米での異常寒波、日本の夏の異常高温、東南アジアの多雨などは、典型的なラニーニャの影響だったとされています。
また、北米、欧州は、2009年から2010年にかけて冬季に異常寒波を経験し、同じ現象が、2010年から2011年にかけての冬季にも起こっています。
これは、主に、北極振動という北極近辺の気圧変動の影響とされていますが、それに加えて、ラニーニャの影響もあるとの指摘もあります。
なお、日本の一部メディアや科学者達は、2010年夏の日本の異常高温がCO2の影響であると示唆したがりました。一方、米国のクリントン女史やアル・ゴアなどの民主党政治家とIPCCの仲間たちは、米国の昨今の異常寒波がCO2による気候変動の影響などと言っています。こうした言い分は、論外なお話であることを知ってほしいものです。
|
2011年2月17日(木)
前回から、地球気温変化の本当の原因は何だったのか、について紹介しています。
今日は、前回の続きで、20世紀が小氷河期からの回復過程にあることを示すデータに関して説明します。
前回では、小氷河期からの回復過程で、0.5℃/100年程度の気温上昇があったとする赤祖父俊一氏の主張を紹介しました。そして、赤祖父氏は、20世紀の気温推移について、図1を示して説明されています。
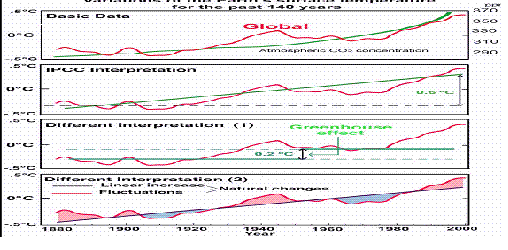
図1 赤祖父氏の主張する20世紀の気温推移 |
上段のグラフは、1880年から2000年までの世界平均気温の推移(赤色:IPCCの気温データ)、大気中CO2濃度の推移(緑色)が示されています。
2段目のグラフは、1880年から2000年の間の気温トレンドが0.6℃上昇したというIPCCの主張を示しています。
3段目のグラフは、大気中CO2が増大した結果、気温が上がったとするIPCCの主張について、1920年〜1980年までの上昇分は0.2℃だった、という意味で示されています。
4段目が肝要なグラフで、直線は0.5℃/100年の勾配を示しています。
このグラフにおいて、赤祖父氏は、20世紀の気温推移は、この直線の上に、準周期的な温暖期、寒冷期の変動分(ピンクや青で塗りつぶした部分)が乗っていたと考えるべきだと、主張しています。
そして、この変動部分は、数十年周期で起きる太平洋振動(PDO)とよく対応しているのです。実際、世界気温データ紹介時に書いたように、北米、北欧、アラスカの気温変化は、PDOの変化と極めてよく一致していました。
赤祖父氏は、IPCCの気温データは一応正しいものとして論理を展開されています。
そして、IPCCデータでは、20世紀の後半の1980年から2000年にかけて約0.6℃上昇したことになっていますが、ここには“まさに人為的な”データ操作が含まれていて、気温数字は倍ぐらい高くなっている可能性が高いのです。
従って、トレンド曲線についての評価は変更が必要でしょう。例えば、1880年から2000年の間の気温トレンドは、0.6℃ではなく0.3℃〜0.4℃程度になり、赤祖父氏の指摘する19世紀からの上昇トレンドも0.5℃ではなく0.4℃以下、といった数字になるのかもしれません。
しかしながら、数字の変更はあっても、気温変化は、小氷河期からの回復直線上に自然の変動分が載っていること、とする赤祖父氏の結論には影響しないでしょう。
IPCCは、20世紀後半の、高々20年程度の範囲だけに特にこだわって気候変動を論じてきました。地球気候の変化を、こうした短期的視野で見てしまったことには、問題があったと思えます。
次回から、IPCCが無視または軽視したもう一つの重要な要素、大気と海洋の周期変動の影響について説明してゆきます。
|
2011年2月14日(月)
前回まで、世界気温データの実態について紹介してきました。そして、「CO2増大が原因で20世紀後半にかつてないほど気温が上昇した」とするCO2温暖化論は、事実とは異なることを指摘してきました。
地球気候や地球気温が20世紀においても変化してきたのは事実です。全体として気温上昇があったことも間違いないと考えられます。そこで、今日からは、地球気温変化の本当の原因は何だったのか、という視点から紹介してゆきます。
CO2温暖化論では、確かな根拠もない時点でCO2増大が異常な高温をもたらすと決めつけ、実際に20世紀後半に気温が急上昇した、としてきました。そしてIPCCは、自分達の結論に対して科学的正当性を強調してきたのです。しかしながら、そこには、科学論として踏むべきステップの無視があったと考えます。
まず第一に、14〜15世紀頃に始まり18世紀後半頃まで続いた寒い時期(小氷河期と呼ばれています)があったことを、無視又は軽視しようとしたことでした。
その結果、20世紀が寒かった小氷河期からの回復過程にあることに関して、十分な論証を怠ったといえるでしょう。
IPCCは、今や有名となった「ホッケースティック」論文を中核思想にしていました。
ホッケースティック論文とは、木の年輪などから過去気温を推定し、「この1000年間で、10〜12世紀の中世温暖期も15〜18世紀の小氷河期もなく、気温はほぼ平坦に推移したが、20世紀後半になって異常に高温になった」とする論文で、その形が図1に示すように、ホッケーのスティックに似ていたことから名づけられました。
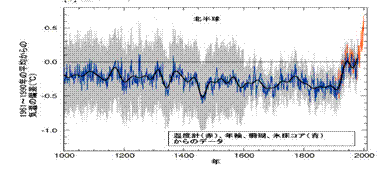
図1 ホッケースティック(IPCC第三次報告書日本語訳より引用)
縦軸は1961年~1990年の平均値からの差異(偏差)℃ |
これは人類史を無視するとんでもない論文でした。地球上では、9世紀から13世紀には温暖期があって文化や文明が栄えた後、18世紀の半ばまで続いた寒い小氷河期が来て、世界の多くの地域で、人類は多大な苦しみを味わったのでした。
ホッケースティック論文は、IPCC内では聖典のごとき扱いを受けました。
20世紀の後半にCO2の大気中濃度が“かつてないほど”に増大した結果、“20世紀後半のかつてない温度上昇”を起している、とする主張にとってこれ以上ない内容だったからです。
しかし、今やホッケースティック論文は、以前に紹介したマッキンタイヤ達によって完全に論破されました。それでもIPCCリーダー達は、何とかしてホッケースティックを守ろうとしました。2007年の第四次報告書に類似論文を“査読つき”として掲載すべく、猛然と画策したのです。この過程における彼らの醜悪極まる行為については『地球温暖化スキャンダル』に詳しく書かれています。
IPCC派の科学者達は、彼らの思想を死守するために、世界気温データにかかる情報を独占している立場を利用して、あろうことか、気温データまで怪しげな操作をして自説を正当化しようとした、と言えるのかもしれません。
そして、それを繕うように、政治家、官僚、IPCCのリーダーは、“IPCCの結論は世界の2500人の科学者の総意である”として、科学論としてまっとうであることを強弁してきたのでないでしょうか。
大切な視点は、長く続いてきた寒い小氷河期から脱却の過程がどうだったかです。
気温上昇が続いたことは、世界各地の氷河が18世紀の初め頃からすでに後退(融解)を開始していた事実からも判ります。そして、こうした長期にわたる気温上昇の原因は、太陽活動の長期的変動に伴う影響以外には考えられないでしょう。
なお、アル・ゴア氏は著書「不都合な真実」で十数ページにわたって各地の氷河の写真を見せて氷河崩壊の話を語り、1970年と2005年時点で氷の量がこんなに違うと示しました。
彼にとっては、現在との比較対象時点が1970年であることが重要でした。即ち、大気中CO2濃度が急速に増加し始めた時期と氷河の後退が一致している、と示唆することが大切だったのです。しかしながら、これはデマの類といわざるをえません。
世界の氷河は、1970年の100年以上前から後退を続けてきたのですから。
以前に紹介した北極圏研究で著名な赤祖父俊一氏は、CO2温暖化論では地球の自然の昇温過程が過少に評価されている、と主張されてきました。
そして、図2のように、気温は1800年頃から持続的(ほぼ直線的)に上昇してきた事実を挙げて、20世紀の気温推移についても考察されています。

図2 過去からの自然の気温変化 |
この図で縦軸は年気温平均の絶対値、上のグラフはICECOREの酸素同位体濃度の測定値から算出した気温(目盛は右側)、中央は北ノルウェーの実際の気温推移、下は北極沿岸での気温推移で、目盛は左側です。下の二つのグラフは、上のグラフの変化の正しさの証拠として示されています。
なお、いずれのグラフにおいても、1920年頃から1940年頃にかけて、大きな気温上昇があったことを示しています。
赤線はトレンド曲線で、100年間で0.5℃程度の上昇があったことになります。
一方、IPCCは、20世紀の100年間で、世界気温は約0.7℃上昇したとしてきました。そして、その大部分がCO2による温度上昇だ、と主張してきたのです。
それに対して、赤祖父氏は、20世紀の気温上昇の大部分がCO2とは無関係な自然の上昇だったのでは、と指摘されているのです。
小氷河期からの回復過程が20世紀に入っていつまで継続したのか、ということについては、根拠となるデータを見出すことは不可能に近いでしょう。
大事なことは、少なくとも、こうした事実を、客観的に、可能ならば、定量的に、評価してから20世紀の話に進むべきだった、ということです。 |
2011年2月7日(月)
昨年11月以来、世界の気温データの実情について紹介してきました。
今回は、 世界平均気温なるものの意味 について考えてみます。
まともなデータは、先進国だけだった
“世界平均”と呼ぶ以上、地球上のあらゆる地表面における気温データが均等に評価されていることが前提です。百歩譲って、測定が困難な砂漠や高山などの特殊地形の地域は除いて考えるとしても、その他の地域では、正確な気温データが存在することが求められます。
しかしながら、現実にはまともなデータが揃っていたのは、いわゆる先進国だけでした。アフリカ、南米、南および東アジア(中国を含む)、中央アジア、中東などの地域において、地域全体をカバーする信頼性の高い長期データはなかったはずです。
そんな中で100年にもわたる期間の世界平均気温が算出できた訳がないのです。
私たちは、CO2が世界の気温にどう影響したかを議論する前に、そして、その指標として世界平均気温なるものを導出する前に、世界平均気温の定義 を明確にすべきでした。
それすら不明確なままに、ああでもない、こうでもないと言ってきたということです。
他地点データが適用された
これまでに説明したことの繰り返しになりますが、世界平均気温は、地球表面を緯度5度、経度5度で分割した格子を単位として計算します。格子内に存在する観測点データから格子内の平均温度を計算し、格子面積で重み付けして加重平均した数字が世界平均温度とされるのでした。
世界全体格子数は約8000、地上の格子点数は2400程度になります。しかし、世界気温データの“元締め”NOAA/NCDCの世界気温データGHCNでは、気温算出に使用する採用観測点は1500程度までに減り、今や、一つも採用観測点が存在しない空格子点が40%強になっています。
気温データの管理者達が “あみ出した”1200kmルールなるものは、現地の気温データに代えて遠隔の他地点データを適用できるとする考え方で、上記の状況を補うのにまことに都合のよい理屈でした。というより、そのために言い出したのかもしれません。
その結果、世界平均気温算出根拠となるデータの少なくとも40%は、その地において実際に計測されたデータではない ということになりました。
では残りの60%の格子内データはどうかといえば、これも説明してきたように、観測点の恣意的な選択がされている可能性が高く、気温が上がっていない田舎の観測点は計算から除外され、都市化によって気温が上昇した地点が優先して残されているようです。
生データが示す真実
本ブログでは、各地の気温生データを見てきました。その結果、20世紀の気温推移は、明らかに、地域によって相当に異なっていたのが実情のようです。
20世紀を通して温暖化すらしていなかった地域があった。
カナダ、シベリア、北極近辺、南極、欧州のいくつかの国、ニュージーランドなど
周期的に変動していただけの地域があった。
北米、北欧、オーストラリア
階段状に上昇してきた地域があった。
日本、アラスカ、
しかしながら、IPCCは、生データに操作を加えた補正値なるものを算出して、各地の気温としてきました。その結果は、生データが示す実態とは、似ても似つかぬ姿に変身させられていました。長期的傾向がこれだけ異なるいろいろな地域の気温データを、ただ集めて平均値を出して意味のある数字と言えるか、という問題提起もあってしかるべきでしょう。
結 論
結論として言えることは、世界平均気温の計算に用いられた気温データは、地域の実態を的確に反映していない数値だったということです。こんなことで世界平均気温を算出したと言えるのだろうか、ということです。
様々な作為が加わって出来上がったこんな数字が一人歩きし、20世紀後半において、CO2が原因でかつてない温度上昇が起き、このまま進むと人類は大変な危機を迎えると、大騒ぎしてきたのです。
世界の人々を馬鹿にした話ではありませんか。 |
2011年2月3日(木)
これまで、主に地上気温データについて説明してきました。今回は大気温度と海面温度についてデータを紹介します。
大気温度について
人工衛星を使用しマイクロ波を利用した大気温度観測は1979年から始まり、約30年のデータ蓄積があります。現在、世界には、英国ハドレーセンター、米国アラバマ大学ハンツビル校(UAH)、RSS社(Remote Sensing System)の三つの組織の大気温度観測データがあり、以下にUAHデータを示します。(RSSも、ほぼ、同じ数字)
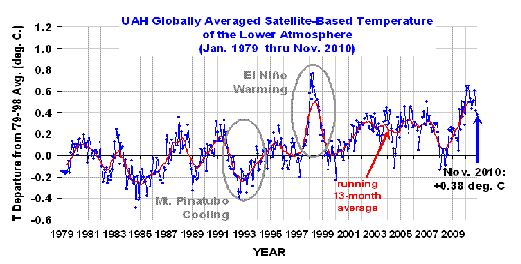
図1 UAHの大気温度データ(ロイ・スペンサー氏のHP*より)
*http://www.drroyspencer.com/ |
1998年と2010年はエルニーニョの影響が出ており、こうした特異点を除けば
1979年から2010年までのトレンドから想定する30年間での気温上昇は、0.3℃〜0.4℃ でした。
これから言えることは、
1)20世紀後半にIPCCの言うような急激な気温上昇を示していないこと。
2)21世紀の気温推移は、横ばいであること。
2010年のエルニーニョによる一時的な上昇がなければ、21世紀の推移は低下気味だったと思われます。要するに、大気温度は明らかにIPCCの主張を支持していません。
図2は、二つの大気温度データ、UAH(赤色の線)、RSS(緑色の線)と、NOAAの世界地上気温データGHCN(紺色の線)の比較図です**。この図では2008年までの推移が載っています。
**Anthony Watts、Joseph D‘Aleo、“SURFACE TEMPERATURE RECORDS:POLICY-DRIVEN DECEPTION?、”SPPI ORIGINAL PAPER
http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/surface_temp.pdf
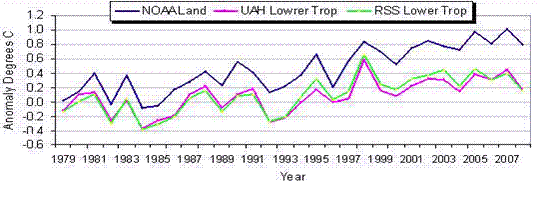
図2 大気温度と地上気温の比較 |
1990年頃から、大気温度データと地上気温データの乖離が進み、1979年と2007年との差は、NOAAの地上気温データでは約0.8℃、大気温度の上昇分0.3〜0.4℃の2倍に近い数字です。GHCN地上気温データは温暖化バイアス(人為的な操作)がかかっており、それがこうした差になっていると推測されます。
気候モデルに基づくCO2温暖化論では、大気温度は地上温度よりも約1.2倍速く、気温が上昇する とされてきました。図2は、事実は全く逆で、地上温度の上昇速度の方が大だったことを示しています。地上温度の温暖化バイアス(気温操作)が大き過ぎることもありますが、理論(仮説)自体がおかしかったことを示しているように思えます。
海面温度について
海面温度データは、地上気温と同様に、英国ハドレーセンター、NASA、NOAAが収集してきました。しかし、海面温度に関して二つの問題点が指摘されていました。
1)過去データは、測定方法の精度がわるく、信頼性が低い
2)過去データは、サンプリング範囲が限定されていた
海面温度の正確なデータが出るようになったのは、2003年以降のこと、であって、NASAのJET Propusion Laboratory が管理しているThe Argo Network という洋上ブイ測定方式が確立して、始めて可能になったようです。
測定方法は、かつてはバケツで海水をくみ上げる方式(Bucket)、パイプを使用しモーターで海水を吸い上げる方式(Intake)が主流でしたが、いずれも誤差が大きかったようです。測定方法もはっきりしないデータが結構あったようで、長期データとしての信頼性に疑問が残ることを示しています。
小氷河期からの回復過程にあった20世紀において、海面温度が上昇傾向にあったことは間違いないでしょう。しかしながら、Argoデータでは、21世紀に入り海面温度は明らかに低下傾向にあります。
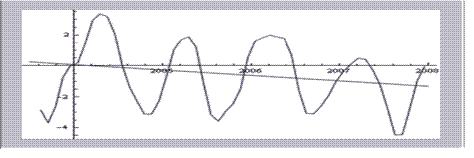
図3 Argoによる海面温度推移(前記ワッツ論文より引用) |
CO2温暖化論者の支持者達は、2009年頃から、地上温度よりも海面温度の方が重要などと言い始めており、昨年、日本の新聞にも似たような話が掲載されていました。
それは、「海洋はここ十数年で0.1℃上昇し、その蓄積熱は、地表温度を30℃も上昇させる量である」として、雑誌Natureに発表するという内容でした。
なぜ、今になってこうした話が騒がれるのでしょうか。海洋の畜熱が大きいとしても(計算すればわかることでは)、20世紀の地上気温は、現実には大して上昇していなかったわけですから。更に言えば、以前の信頼性の低いデータを用いて、定量的な議論をするのは問題ではないか、とも思えます。
なお、ワッツ達は、海面温度もCO2温暖化論支持の組織の管轄下にあるので、地上温度と同様にデータ操作されるのが心配だと書いています。
|
2011年1月31日(月)
今日は、あらためて 都市温暖化の問題 について書きます。
(論争と背景)
今や、先進国住民の80%近くが都市に住み、発展途上国においても約50%が都市に住んでいます。そして、どの都市でもヒートアイランド現象(Urban
Heat Island Effect:UHI)によって都市気温は上昇しました。
それは、人口増に伴う排出熱の増大だけでなく、通風の悪化、道路舗装化、畑地の減少、河川の地下化などによる水蒸発の低下、建物や道路による蓄熱効果の増大、等などが原因とされています。
実際、この数十年間に、世界の多くの都市において都市化が原因で気温が数℃上昇しています。因みに東京では、1950年以降で都市化により2℃強、気温上昇しています。都市化はじわじわと進行してきたので、都市住民が時々において都市温暖化を敏感に感じてきたとは思えないですが、今や都市住民は、かつてより相当に高温環境下で生活していることは間違いないのです。
気象庁HPには日本および世界気温の推移が掲載されています。そのデータの下に、わざわざ、“都市温暖化は除かれています”と注書きがされています。なぜこんな注釈をつけているのでしょうか。それは、以下の話から理解できると思います。
IPCCは、“20世紀後半のかつてない気温上昇は、CO2が原因である”と主張してきました。そして、2007年発表の第四次報告書には「20世紀後半における気温上昇のほとんどは、温室効果ガスの増加によるとほぼ断定できます」とされたのでした。
IPCCは、1990年にCRUのフィル・ジョーンズ氏が発表した論文の結論、「都市化の影響は、100年で0.06℃程度の影響」を最大の根拠として、“都市化の影響は極めて小さい”を金科玉条としてきたのです。
一方で、CO2温暖化論に懐疑的な人達は、地上の温度計の読みが上がったのは、都市化が主な原因の一つでないか、と疑ってきました。それに対して、
CO2温暖化論を支持する人達は、様々な理由を上げてこれを否定しようとしてきました。“都市温暖化は除かれています”は、そうした背景もあったのでしょう。
そしてこの論文およびIPCCの結論は、IPCC派と懐疑派の10年にわたる争点の一つになりました。懐疑派は論文使用の気温データの開示要求を繰り返し、IPCC派は提出を頑として拒んだからでした。
こうした経緯は、前に紹介した渡辺教授訳『地球温暖化スキャンダル』に詳細が書かれています。そして今や、ジョーンズ論文も、その後にIPCC派の人達から発表された論文も、対象とした気温データに問題があったことが明らかにされました。
(都市温暖化の定量化)
都市化による気温上昇△Tと人口数Pは、以下の関係式が適用できるとされています。
△T=mLOG(P)+n(m、nは場所によって異なる定数)
定数mやnは、人口密度、都市の構造などによって固有の値になります。そして、人口が1000人ぐらいからこうした影響があるとする論文もあれば、10万人ぐらいまでは影響は小さいとする論文もあるようです。
日本では、既に紹介したように、東北大学名誉教授の近藤純正先生が、都市温暖化の影響を解析されご自身のHP http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/ で公表されています。 それによると、気象庁が年平均温度の算出に使用し都市化の影響が比較的少ないとされる全国17か所の観測点でも、以下のような都市化による温度上昇があると推算されています(単位は℃)
網走(0.35)、石巻(0.30)、山形(0.64)、銚子(0.23)、水戸(0.55)、
長野(0.55)、飯田(0.39)、彦根(0.49)、境(0.39)、浜田(0.38)、
多度津(0.60)、宮崎(1.0)、名瀬(0.26)、石垣島(0.31)
(根室、寿都、伏木はデータなし)
こうした数字を見ても、“都市化の影響は除去されている”という言い分は、間違いと言えるように思われます。
近藤先生は、規模別の都市温暖化の量も推算されていて、図1、2のように整理されています。いずれの都市でも、1960年〜1980年頃に急速に都市温暖化が進み、2000年には、概略、飽和している 様子が分かります。
海外の主要都市も、20世紀中央あたりから都市化が急速に進行し、20世紀末頃には、概ね、進行速度は低下していました。これらの都市における都市温暖化推移も、日本と似た推移をしたはずです。
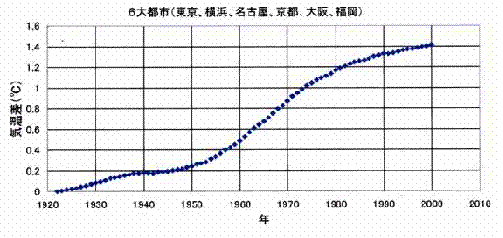
図1 6大都市の都市温暖化の量(1920年〜2000年で 約1.4℃上昇) |

図2 県庁所在都市34の平均の都市温暖化の量(1930年〜2000年で1℃上昇) |
(CO2温暖化論と都市化問題)
都市面積が地表面積全体に占める割合は数%程度です。もし、地表温度が地球上で均等に測定され、測定結果も正確で、世界平均気温が正しい手段で算出されたとしたら、都市温暖化の影響はそれほど大きくないのかも知れません。
しかしながら、これまで本ブログで紹介してきたように、現実は、気温測定場所は偏在していたし、気温データが正確であるとは言い難い実態でした。
何よりも、気温データの管理者達(IPCC派)は、温度が上がっていない田舎のデータを除外し、生データを操作して気温上昇を見せかけました。
また、1200kmルールなどという論理を持ち出し、低温の観測点データを除外して、都市温暖化で気温上昇した遠隔他地点データを代替適用することによって、計算値を意図的に高くした可能性が高いのです。
“都市化の影響は極めて小さい”どころか、“都市温暖化がフルに悪用された”、といっても過言ではありません。“20世紀後半のかつてない気温上昇”は、こうした気温データに恣意的操作が加わり作り上げられたお話だった、という疑惑が濃厚なのです。
(21世紀の気温上昇は止まった)
21世紀に入りIPCCのデータでさえも地上気温上昇は止まっています。そして、大気温度も海面温度も低下傾向を示しています。
クライメートゲート事件の流出メールの中で、リーダーの一人、米国大気研究センター(NCAR)のケビン・トレンバース氏が2009年10月、仲間に宛てて、こうつぶやきました。“最近、温度上昇がみられないのは何故なのだ”と。
21世紀に入り既存都市では気温上昇速度は低下したし、新たな都市の興隆も少なくなりました。気温管理者達にとって、都市化で上昇した気温データを利用することで気温上昇を“実現”してきた“ネタもと”がなくなった、ということなのでしょうか。
CO2温暖化論は、大気中に増加を続けるCO2が地上気温を異常に上昇させているとして、過去30年にわたり世界を揺るがしてきました。
しかしながら、世界気温データから読み取れる気候変動の状況は、世の中で喧伝されてきた話とは、相当に違うということです。
米国では、メディアによるクライメートゲート事件追及があり、“温度データ詐欺”も国民に知らされてきました。だから、米国民は、いまや、呆れているという話も伝わっています。
我が日本では、こうした情報は一切報道されず、いまだに“地球温暖化”という言葉が横行しているし、CO2削減のための温暖化法案の処理が議論されています。
今や、“直ちにCO2を削減すべし”の命題も完全に論拠を失ったのでないでしょうか。こんな愚かな話は速やかに終わりにすべきだと思います。
|
2011年1月27日(木)
欧州の気温データ
これまで繰り返し紹介してきたE.M.Smith氏の検証* によると、NOAA/NCDCのGHCNでは、欧州全体の採用観測点は1980年に600あったのが、1990年には300にまで半減しています。そして、平均気温は、この間に1℃弱、上昇しました。
* http://chiefio.worldpress.com/2010/03/30/europe-atlantic-and-coastal/
そして、高度地点や北の寒い地域の観測点が減少していて、地中海に面した暖かい地域の観測点が増えていると指摘しています。
以下に、欧州の主な国の気温データ(生データ)の推移を示します。
ギザギザしたグラフは月平均気温(生データ)です。月平均値が色を変えて掲載されており、中央に平均値推移とトレンド曲線が見えます。
目盛がはっきり見えないのですが、横軸は、下部に小さく薄く見える目盛間隔が3年で、右端は2007年、全体で300年間位の期間の推移となっています。縦軸は℃表示で、目盛間隔は1℃のようです。

図1 オランダの気温推移 |
図1はオランダの気温です。19世紀の終盤と20世紀中盤において、現在よりも1℃以上温暖な時期があったことが判りますが、20世紀後半はほぼ横ばいです。少なくとも、IPCCが主張する“20世紀後半のかつてない温暖化”はここでは、明確にノーです。 また、期間全体のトレンド曲線もほぼフラットのように見えます。
図2はフランス、図3はポルトガル、図4はスペイン、図5はベルギーの気温推移です。
いずれにおいても、長期の気温トレンドは、オランダの場合と同様に、横ばいか低下傾向だったのに、1990頃から不自然に上昇しています。
なお、黄色線は採用観測点数の変化ですが、フランス、ポルトガルでは間引きと温度上昇に相関が見られますが、スペインでは脈絡なく極端に変化していることがわかります。
こうした経過とデータから判断すると、オランダ以外の国々においても、“20世紀後半にかつてない気温上昇があった”という主張には疑問符がつくように思います。
各国の1990年以降の気温上昇は、観測点の大幅間引きを含むNOAAのおかしなデータ操作の結果が現れているのでないかと推測します。
その他地域の気温推移
以下はワッツの論文“SURFACE TEMPERATURE RECORDS:POLICY-DRIVEN DECEPTION?、”SPPI ORIGINAL PAPER *および E.M.SmithのHP掲載論文からの引用です。
*http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/surface_temp.pdf
(1)中国
GHCNの採用観測点数は、1980年頃の400から1990年には50以下に激減しました。その結果、1990年以降で1℃程度上昇したことになっています。
気温データは都市化の影響も出ていると推測されていて、あのフィル・ジョーンズでさえ、中国の気温データは1℃/100年ぐらいは高い(誤差)と言っているようです。
http://chiefio.worldpress.com/2009/10/28/ghcn-china-the-dragon-ate-my-themometers/
(2)アフリカ
GHCN採用観測点数は、1990年頃に40%程度減少し、300以下となりました。そして、平均気温は1℃弱上がったことになっています。E.M.Smithは、モロッコ海岸の低温を示す観測点は消され、代わりに、サハラの高温を示す観測点が増加していると指摘しています。 http://chiefio.worldpress.com/2009/12/01/ncdc-ghcn-africa-byaltitude/
(3)南アメリカ
GHCN採用観測点数は、1980年頃の300から、1990年には200まで減少しました。そして、平均気温は1950年以来、40年間ほどほぼ一定に推移していたのに対し、1990年以降で1℃程度急に上昇したことになっています。
ワッツは、高地の観測点はほとんどはずされており、海岸地域の観測点が相対的に増加した、と指摘しています。
クライメートゲート事件の直後、有名になった話があります。
NASAが発表していた世界の気温分布図では、高山地域ボリビアの気温が他地域と比べて高い上昇があったと、されていました。ところが、ある人が観測点データの内容を検査したところ、ボリビアの観測点は全てはずされていて、1200kmルールによって、チリの海岸地域のデータとアマゾンの地域のデータで代替されていたことがわかったのです。
(4)インド
インドの気温は1950年から1975年ぐらいまで、一定に推移していましが、
1985年頃から1℃程度上昇しています。一方で、採用観測点数も、1985年頃20%減少しており、相関が見られます。なお、ワッツ達は、計測気温上昇の理由として都市化を挙げています。
こうした発展途上国においては、1950年以前のデータの信頼性には、かなり疑問があると考えます。また、最近のデータは気温観測点が都市近辺に大きく偏っており、20世紀後半の都市化進展の影響大であることが、容易に、推測されます。
更に、NOAA/NCDCによるデータ操作も加わっており、これらの地域の気温データ全体の信頼性には問題があると思われます。少なくとも、1990年以降での1℃近い計測気温上昇は、疑問符を付けて見るべきと考えます。 (終わり)
|
2011年1月24日(月)
オーストラリア気象庁(the Australian Bureau of Meteorology (BOM))は、豪州の20世紀の気温推移は図1のようだった、としていました。
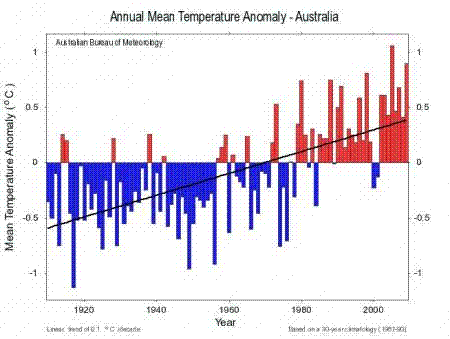
図1 オーストラリア気象庁発表の気温推移
(WUWT より引用) |
1910年頃から2009年までの気温が、平均値との差異(Anomaly)で示されています(平均値の基準は不明)。そして、気温トレンド(図の直線)は、20世紀を通じ右肩上がりだったという話になっていたのです。
Ken Stewartと言う人が、豪州のAustralian ?High-Quality Climate Site Network(以下HQ)という気温データを検証していて、ワッツのブログWUWTが、その記事を2010年7月27日に掲載しています。
HQは、BOMが、従来の気温データの改良版と位置づけしているもので、図2は、その観測点の分布です。
100ケ所の観測点が存在しますが、実際に気温算出に使われる観測点は、2000年以降に約半分に激減したようです。
そして、スチュアート氏は、HQでは、都市部のデータが利用され、不連続なデータしかなく、短期間のデータしかない観測点が多く、それを補うために推測値が使用されている、と指摘しました。
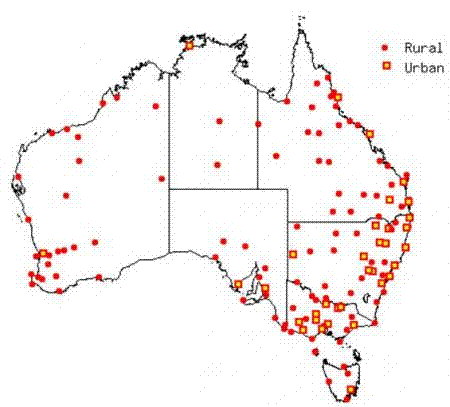
図2 HQの気温観測点 |
スチュアート氏は、HQに関して、1910年から2009年までの、生データとBOMが補正したデータを比較しました。その結果が図3で、青が生データ、赤がBOMの補正後データです。補正後は、公式発表の図1と大体似ています。
補正後データは、1910年から1950年の気温値が、低い数値に補正されています。これは、ニュージーランドの場合と同様の補正の手口であって、その結果、トレンド曲線は、生データでは0.6℃/100年だったのが、補正後は0.85℃/100年と上がっています。
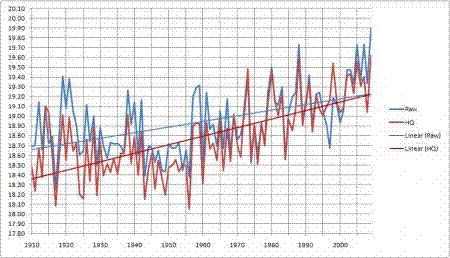
図3 生データ(青線)とBOMの補正後データ(赤線)の比較 |
NOAAのGHCN の豪州データについても、生データを補正データと比較した人がいます。ダーウイン空港という場所に設置された温度計のデータ(図4)です。
生データでは20世紀を通して寒冷化していたのに(青線)、補正データでは、見事な上昇傾向が“実現”されていたのでした(赤線)。
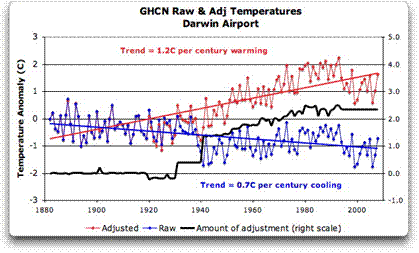
図4 豪州の一観測点の生データと補正データ比較 |
結局、豪州の公式気温データも、おかしな操作の結果だった、ということなのでしょう。
|
2011年1月20日(木)
今回と次回の2回にわたって、オセアニア地域(豪州とニュージーランド)の気温推移について紹介します。
(IPCCのデータ)
下図1は、これまでに繰り返し紹介してきた2007年のIPCCの第四次報告書に載ったオセアニア地域(北と南に分かれている)の気温データです。
ここでも、20世紀後半に右肩上がりに推移した、となっているのですが、他の地域では軒並み1℃近い上昇だったとしていたのに対し、この地域は0.5℃程度とやや小さくなっています。
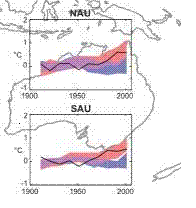
図1 IPCC発表のオセアニアの気温推移 |
(ニュージーランドの気温データ)
クライメートゲート事件勃発直後の2009年11月25日、ニュージーランド気候科学連合の関係者が、ニュージーランド国立水圏気圏研究所(NIWA)が発表したニュージーランドの公式気温データにクレームをつけています。
NIWAデータでは、IPCCデータを裏付けるように、気温は図2の如く推移したとされていました。
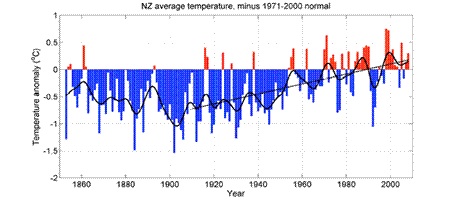
図2 NIWA発表のNZの気温推移 |
1971年から2000年の平均値との差異(℃)で示されており、直線は気温推移のトレンドを表しています。図から判るように、トレンドは、1900年頃からほぼ一直線に上昇したことになっていたのです。
しかしながら、ニュージーランド気候科学連合の関係者達は、NZの気温の生データを調べたところ、このような一直線の昇温傾向はなく、図3のように、20世紀を通して小さな変動を繰り返していただけ だった、としてNIWAのおかしな操作を指摘したのです。
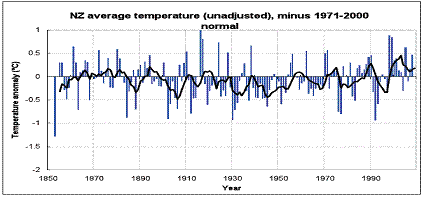
図3 NZの気温生データの推移 |
両図の大きな違いは、NIWA発表図では、1900年から1950頃にかけて、生データの大幅な低下の操作がされていることです。これは、これまでに紹介したNOAAのおなじみの手段が使われた可能性が高く、1950年以前を低くみせることで、“20世紀後半における右肩上がりの温暖化を明確にしようとした”と考えられる結果でした。
|
2011年1月17日(月)
米国気温データについて紹介します。
米国の気温データとして、NOAA/NCDCのUSHCNと、NASAのGISSの二つが知られています。
既に紹介したように、USHCNは、測定データの信頼性に大変な問題があり、都市温暖化の補正もされておらず、加えて、とんでもないおかしな操作が施されていました。
USHCNの採用観測点は2005年頃から急速に減り、今や、全米で200を切っており、飛行場内設置の観測点比率が大幅に増加しているようです。
従って以下には、GISSデータを紹介します。但し、GISSも、元データの多くはGHCNに依存していることや、GISS自体でも変な操作がされているという指摘もあって、信頼性に疑問がないわけではないようです。
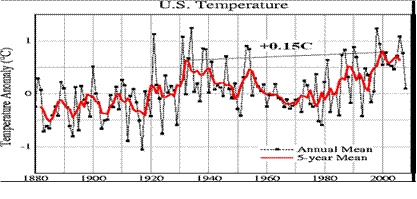
図1 GISSによる米国気温データ(*) |
*Anthony Watts、Joseph D‘Aleo、“SURFACE TEMPERATURE RECORDS:POLICY-DRIVEN DECEPTION?、”SPPI ORIGINAL PAPERより(本欄NO5で紹介)
図1は、1880年から2008年までのデータが載っています。
これから、1900年から2000年の100年間の気温上昇は0.7〜0.8℃と読み取れます。この上昇トレンドの中には、寒かった小氷河期からの回復過程による自然上昇分が含まれているはずです。
温暖化論者達は、2000年以降も気温が上昇過程にあると言っているようですが、21世紀に入ってからの大気温度や海面温度データ推移から判断して、2000年頃がピークだったことは明らかと思われます。
結局、米国気温の推移は、19世紀後半から現在までの間に、1940年頃と、20世紀後半の、二つの温度ピークを示しています。上図において後半ピークがわずかに高いことについて、ワッツ達は、都市温暖化分をまだ含むので正しく補正すれば1940年ピークより低いと見ています。
米国気温推移は、以下の二つの図の比較から判るように、太平洋における数十年規模の振動現象であるPacific Decadal Oscillation(PDO)の変化とよく一致しています。
PDO指数がプラス(赤)の時は二つの気温ピークと一致し、指数がマイナス(青)の時は気温低下の時期に合っています。
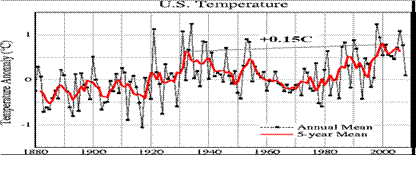
図1の再掲 |

図2 太平洋数十年規模の振動現象(PDO) |
米国気温についても、CO2の増加が原因で20世紀後半に異常に気温上昇した とするIPCCの主張には合理性が見出せません。
20世紀における米国の気温推移は、地球気候の小氷河期きからの回復と、大気や海洋の影響を受けて、自然の変動を示していただけ、だったのでないでしょうか。
|
2011年1月13日(木)
本ブログでは、昨年11月以降、国連の気候変動にかかる政府間パネル(IPCC)発表の20世紀以降の気温数字は正しかったのか、という観点から、世界各地の気温データの生の姿を紹介してきました。未紹介だった地域がありますので、今年も、これから数回にわたって、そうした地域の気温データを検証したいと思います。今回は、日本の気温推移について述べます。
図1は気象庁HPより引用した1900年以降の日本の気温推移です。
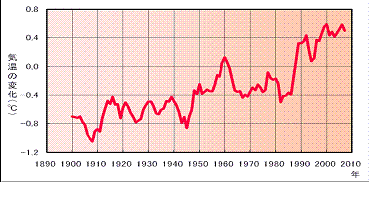
図1 日本の20世紀の気温推移(気象庁HPより引用)
(1971年から2000年までの平均値からの差) |
気象庁は、都市化の気温への影響が比較的少ない17地点データをもとにしているとし、HPにおいて以下のように解説されています。
『日本の平均気温は、1898年(明治31年)以降では100年あたりおよそ1.1℃の割合で上昇しています。特に、1990年代以降、高温となる年が頻繁にあらわれています。
日本の気温上昇が世界の平均に比べて大きいのは、日本が、地球温暖化による気温の上昇率が比較的大きい北半球の中緯度に位置しているためと考えられます。』
既に紹介した東北大学名誉教授の近藤純正先生*は、17箇所の都市温暖化について検証され、以下の結果を報告されています。(単位は℃、根室、寿都、伏木はデータなし)網走(0.35)、石巻(0.30)、山形(0.64)、銚子(0.23)、水戸(0.55)、長野(0.55)、飯田(0.39)、彦根(0.49)、境(0.39)、浜田(0.38)、多度津(0.60)、宮崎(1.0)、名瀬(0.26)、石垣島(0.31)
20世紀後半にかなりの都市温暖化があったことは事実でしょう。1.1℃/100年間という数字は、都市化を含まないとするのなら、下方修正が必要なように思います。
「北半球の中緯度だから気温が上昇し易い」という理屈は、これまでに説明してきたように、もっと寒い地域の気温推移の実態(もっと高緯度でもほとんど温度上昇していなかった所は沢山あった)を考えると、明らかに間違いと言えるのでないでしょうか。
なお近藤先生は、全国の約50ケ所の観測点を選択し実態調査され、周辺観測点のデータとの比較を通して、日だまり効果や都市温暖化分を含まない自然の温暖化量を算出されました。その結果、日本の気温推移は、Y=0.0067X+0.1962(Xは年、Yは℃)の回帰曲線で表せるとして、1890年〜2000年の間の 自然変動は約0.7℃程度 だったと報告されています。気象庁発表の1.1℃よりは、0.4℃低い数字です。
近藤先生は、また、日本の気温推移について、以下を指摘されています。
1)1913年、1946年、1988年に、計3回の温度ジャンプがあったこと
2)ジャンプ時と次のジャンプ時の間は、気温がほぼ安定して推移したこと
年度ごとの特異点(例えば、1960年頃)はありますが、1950年から1980年までの30年間、1990年以降の20年間において、気温は、平均的には一定に推移したと見るのが妥当なように思えます。
このことは、日本の気温上昇にCO2増加の影響が大だった、とすることを否定しているように思えます。20世紀後半を通して次第に大気中濃度が増大したCO2が原因ならば、このような長期にわたる定温期間があるのは不自然でしょう。
なお、近藤先生は、ジャンプと太陽黒点相対数が極小から極大に向かう転換期が一致するとされ、1913年と1988年は、その前に世界的に火山の大噴火が頻発した結果、気温が低下した反動だったという見方、1946年頃のジャンプは三陸沖の海水温ジャンプ(1.4℃程度も急上昇)が大きく影響した、とする見方を指摘されています。
日本の20世紀の気温推移は、寒かった小氷河期からの自然の復による上昇分の上に、都市温暖化、太陽活動変化の影響、海洋・大気の活動の変化、などの変動要因が加わっていると考えられます。そして、日本の気温推移は、ほとんどが自然変動であって、
CO2による気温上昇の影響は極めて小さかった、と結論できるように思います。
*参考文献 近藤純正氏HP http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/
K39 気温の日だまり効果の補正(2)
http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke39.html
K40 基準34地点による日本の温暖化量
http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke40.html
K41 都市の温暖化量、全国91都市
http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke41.html
|
2010年12月20日(月)
これまで数回にわたり寒い地域の気温推移について紹介し、CO2温暖化論の根幹をなしていた水蒸気ポジティブフィードバック論という仮説についても言及してきました。
今回は、CO2の温室効果に関する理論を紹介し、上記仮説との関連について説明します。
(1)温室効果理論
CO2温暖化論では、地表面が放射する熱線(赤外線)をCO2が吸収した後、地表に向かって再放射するから地球が温暖化するとされてきました。
地表面が発する熱線を吸収する物質を“温室効果ガス”とよび、最大のものは水蒸気で、地球が放出する熱線の内、90%以上は水蒸気による吸収で、残りがCO2等による吸収と計算されているようです。
CO2は、地球が放出する熱線の内、水蒸気が吸収しない波長15μ(ミクロン)近辺の熱線を効率よく吸収することがCO2温暖化論が広がった理由の一つでした。
なお、再放射の大きさは放射強制力と呼ばれ、1平方メートル当たりのワット数(W)で表します。
(2)CO2の温室効果
図1は、エッセンバック(Willis Eschenbach)という人が2006年にブログClimate Auditに掲載したCO2の温室効果にかかるデータです。
図1の青い線がCO2による温室効果を示し、縦軸は大気から地表面に向かう下向きの放射強制力で、横軸は大気中CO2濃度で表されています。CO2濃度がゼロの時が水蒸気による分を意味しており、235ワット/m2程度の放射強制力になっています。
つまり、図1は、CO2濃度の変化とともに、CO2による放射強制力がどう追加されるかを示しています。
容易に判るように、CO2による放射強制力の変化は対数(Logarism)曲線的で、図にあるように、放射強制力(ワット/m2)=2.94*LOG(2CO?)+233.6 という式であらわされています。対数曲線なので、濃度の増大とともに、増加分による放射強制力の追加分は減少してゆきます。
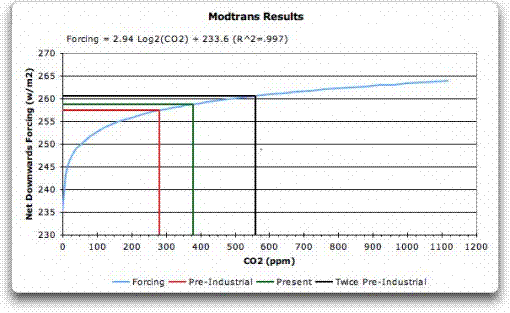
図1 大気中CO2濃度と放射強制力の関係
David ArchibaldによるWUWT2010年3月8日号解説記事より抜粋 |
赤線は産業革命前の大気中CO2濃度(280ppm)、緑線は現在(380ppm)、黒線は産業革命前の2倍の濃度(560ppm)の位置を示しています。
CO2濃度が100ppmのときに現在の放射強制力の80%に達し、氷河時代の大気中CO2濃度の推定値とされる180ppmのときに、現在の放射強制力の90%に達していたという計算になります。また、産業革命前の2倍の濃度における放射強制力は、現在より6%増加するだけです。
CO2温暖化論に対する反論者の意見としてよく言われてきた、“CO2による吸収は既に飽和している”という言い分は、こうした図から理解できます。
図2は、大気中CO2濃度の増加分(20ppmで区分)が、大気温度の上昇にどれだけ寄与するかを示しています。縦軸は温度(℃)になっています。
大気中濃度がゼロの時から20ppmに増えた時が、約1.7℃の最大の上昇を示し、その後の追加増分による大気温度上昇は、ずっと小さく、漸減してゆきます。
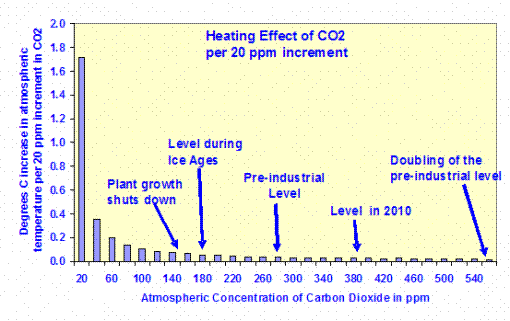
図2 CO2濃度の追加増分と大気温度上昇分の関係
(データソースは図1と同じ) |
この図から、次のことが読み取れます。
大気中CO2濃度が、産業革命前の280ppmから現在の380ppmに増加したことによる気温上昇への寄与分は0.2℃程度(この間の各20ppm増加の寄与分の合計)、また、大気中CO2濃度が現状の380ppmから、産業革命前の倍の560ppmになったときの気温上昇へ寄与分も、同じ0.2℃程度となる。
しかしながら、IPCCは、このままCO2排出が続き21世紀末にCO2濃度が2倍になると、気温が数℃も上昇すると警告していました。しかしながら、CO2濃度が増加しただけでは、そんな大きな気温上昇は見込めません。何が違うのでしょうか。
それは、IPCCの主張が水蒸気ポジティブフィードバック仮説に基づいていたからでした。それは、水蒸気が大きな温室効果を有することから『大気中CO2増加による地表面の加熱が地表面からの水蒸気の蒸発を促進し、大気中水蒸気濃度を増大させ、その増加した水蒸気によって地表面が更に暖められる』とする考え方でした。
そして、寒い地域は大気中水蒸気濃度が低く、水蒸気濃度は上昇しやすい、とされ、「水蒸気ポジティブフィードバックは、寒い地域で効果が大きい」が主張されました。
IPCC報告書における 20世紀の気温推移の再現も、21世紀の気温変化予測も、こうした理屈が存分に応用されたのです。
寒い所は、IPCCのCO2温暖化論の正当性が顕著に示される場所のはずでした。
しかしながら、20世紀後半に大気中CO2濃度増大が明らかであったにもかかわらず、北欧、カナダ、シベリア、アラスカ、北極、南極、グリーンランドなどの、寒い地域の気温データは、IPCCの主張のように上昇していませんでした。
なお、CO2温暖化論では、大気上部に高温の場所(HotSpot)があることが前提でした。しかしながら、この20年間、衛星観測で調査を続けてきたにもかかわらず、HotSpotはついに見つからなかったようです。
世界各地のほんとうの気温データは、CO2温暖化論の基本原理も支持していないということなのでしょう。
|
2010年12月16日(木)
IPCCの言う「“寒いところは気温が上がり易い”」は、ほんとうだったのか の検証の第6回(最終回)として、南極およびグリーンランドの気温データについて紹介します。
(海面上昇の怖い話)
アル・ゴア氏は、「不都合な真実」で、南極とグリーンランドの氷の半分が海に落ちたら、6mもの海面上昇が起きて世界が水浸しになると、我々を脅しました。
そうした根拠として、ゴア氏は、南極半島とその周辺に着目して気温が上昇しているといい、氷河に出来ている割れ目とか末端で氷河が崩落する写真などを、たくさん見せてくれました。そして、半島のラーセンBという棚氷が融解・崩壊して消失したとして、CO2による地球温暖化の証拠としたのでした。
でもこれは、科学者の常識とはかなり違っていたようです。氷河が末端で崩落するのも割れ目が生じるのも当たり前の話でしたし、ラーセンB棚氷は、過去においても消えた時代があったらしいのです。
南極半島あたりは気温変化が起こりやすく、棚氷の融解も20世紀後半に起きた特異的現象でなかったとされていました。
だからゴア氏の仲間のIPCCでさえ、さすがに『南極の温度上昇や氷雪の減少についての明白な証拠はない』として、南極崩壊のようなシナリオには言及していません。
ゴア氏の怖い話は単なる仮定の話であり、例えて言えば、“もし地球が爆発したら人類はみんな死ぬ”の類の話かもしれません。
(南極各地の気温推移)
南極についての調査は1950年代に開始されました。下図1は、これまでに各国が建設した観測基地周辺における気温推移データです。
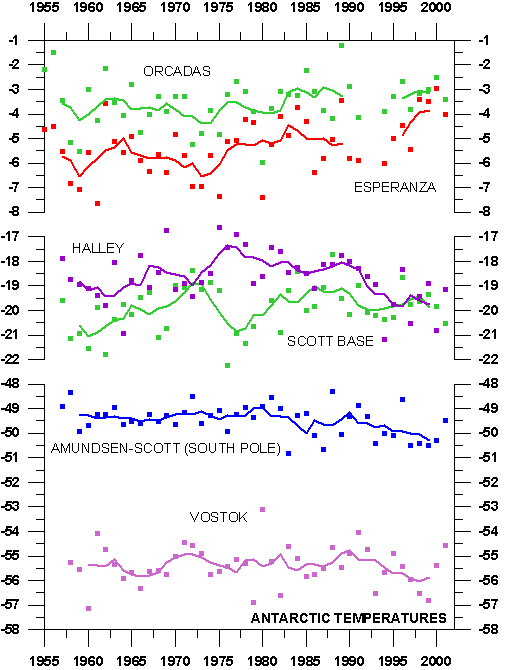
図1 南極各地の気温推移 |
上の二つのグラフOrcadas および Esperanzaは南極半島にあり、20世紀後半にやや温暖化している様子が見られますが、他のグラフは東南極や内陸部の地点で、20世紀の後半でも気温は上がっていません。どちらかといえば寒冷化気味に推移しています。
南半球における大気や海洋の振動現象が、南極の一部の気候に影響しているはずですが、南極についての情報は北極に比べて、まだ、少ないようです。
CO2温暖化論を信じる人達の間では、衛星データから西南極(特に沿岸部)温度が上昇しているとする意見もあるようです。しかし、CO2が南極気温に影響したというのなら内陸部でも何らかの兆候が見られるはずでしょう。これまでに紹介してきた北の寒い地域の実態から考えても、西南極の一部が、仮に、温暖化していようとも、それはCO2の話とは無関係と言えるように思えます。
南極についての大方の科学者の意見は、以下のようです。
1. 南極大陸の温度は、横ばいか又は低下している。
2. 周辺温度が上昇したとしても、もともと温度が低い(−50℃)ため融解はせず、逆に温度上昇による水蒸気増加が、降雨(雪)となって、氷雪増加をもたらす。
3. 南極の氷雪増加は、重さによる大陸の沈降によって海面低下をもたらす
ゴア氏を始め、CO2温暖化論者の人達は、南極には高い関心を寄せてきましたが、IPCC発表の世界平均気温では南極データは含まれていませんでした。そして、もし、広大なこの大陸の、ほとんど変化していなかった気温データが含まれれば、世界平均気温の数字は30%程度は低下するはず、とも、指摘されています。
(グリーンランドの話)
グリーランドの20世紀の気温は、周辺地域の北米、欧州と比較して、やや異なった推移を示していたようです。1920年頃に最も気温が高かった時があり、その後1992年頃まで低下を続けました。
20世紀後半は、海岸よりの氷が減少しているのに対し、内陸部では増加しているとされています。
グリーンランドの気温データは、観測点数も少なく海岸周辺データが主力になっているようなので、ほんとうに島全体の平均的な姿を反映しているのか、疑問なしとは言えないかも知れません。
ゴア氏は、グリーンランドの1992年と2005年の衛星写真を比較して見せて、『グリーランドの氷は加速度的に消滅している』と書きましたが、これは明らかに不適切な比較でした。
1992年頃は、20世紀でグリーンランドの気温が最も低かったからです。どこの氷も、気温が上がれば解けて減少するのは当然です。
なお、グリーンランドが20世紀で最も暖かかった1920年頃にも氷は減少していた という事実を追記しておきます。
(海洋の熱塩循環の話)
海洋には大きな流れがあり、大西洋では南の方から表層を流れて来る暖かい海水がグリーンランド近辺で底部に沈み込んで南に戻ってゆくことが判っています。この沈み込みは、流れの途中で塩分が増大する結果とされてきました。それで熱塩循環と呼ばれています。
大昔、この熱塩循環が止まったことがありました。
氷河時代が終わった時、氷が解けて北米大陸に巨大な淡水湖ができましたが、なにかの拍子でこれが破壊して、北大西洋に大量の淡水が一気に流れこんだのです。その結果、海水の塩分が低下し、海水の沈み込みが無くなり、海流が止まってしまった、というのです。
そして、暖かい海水が来なくなった結果、北米、欧州は、氷河時代に舞い戻ったというのです。
ゴア氏の本の中にもこの話が出てきます。ゴア氏は、グリーランドの氷(淡水)を、大昔の北米の淡水湖に擬せようとしたのでした。そして、CO2が増大すると同じようなことが起こるかもしれないかのように、怖い暗示をしたのでした。
熱塩循環停止の恐怖は、CO2温暖化論の強調話として一時期は有名になりました。しかしながら、今日、海流循環の駆動力は、風と潮汐の影響とする意見が主流のようです。
(まとめ)
IPCCの主張の一つ“寒い所は気温があがりやすい”はほんとうだったのか、というテーマで、数回にわたって寒い地域の気温データを紹介してきました。
IPCCの理屈をもう一度整理すると、以下のようでした。
1)大気中CO2が増大した20世紀後半において、CO2の所為でかつてないほどに気温が上がった。
2)20世紀の気温上昇の大部分は、北半球の寒い地域の気温上昇だった。
3)北の寒い地域の温度上昇は、水蒸気ポジティブフィードバック効果(仮説)が働くことが原因。
4)コンピュータシミュレーションによれば、21世紀は、その継続で、更に気温上昇する。
しかしながら、これまで見てきた寒い地域の気温データが明らかにしていることは、
IPCCの言い分は、全てにおいて、“明らかに事実とは異なっていた”
ということのようです。
かなり広範囲な寒い地域で、気温は上昇するどころか、低下していた可能性があったし、全ての寒い地域で、20世紀後半に気温が急上昇した所は、存在しなかったし、水蒸気ポジティブフィードバック効果の影響も、どこにも見出せなかった
のでした。
考えてみれば、水蒸気ポジティブフィードバック効果というのは、CO2温暖化論者達の主張する仮説 に過ぎませんでした。そんな仮説の証拠は何一つ見いだせなかった、ということなのでしょう。
それでもまだ、“地球温暖化”と“CO2削減話” が叫ばれるのは、どうしたことなのでしょう。
|
2010年12月13日(月)
IPCCの言う「“寒いところは気温が上がり易い”は、ほんとうだったのか」の検証の第5回目として、北極近辺の気温データについて紹介します。
(気温データ)
下図は、オーストラリアの故デーリー(John Daily)という人が集めた北極近辺の気温データで、ソースはNASA/GISSやHad/CRUとなっています。
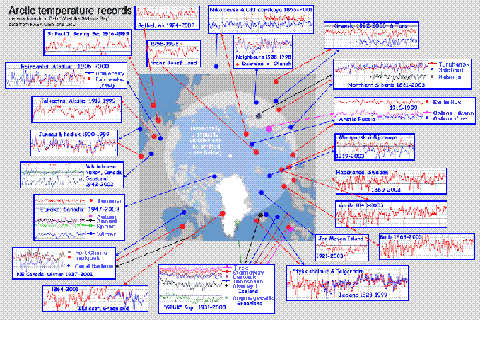
図1 デーリー氏のウェッブサイト "What the Stations Say" 掲載の北極周辺データ
以下より引用
www.greenworldtrust.org.uk/Science/Scientific/Arctic.htm 2009年9月14日号 |
各々の図は小さくて判りにくいのですが、どの場所も、20世紀の気温トレンド曲線は水平に近く20世紀後半に特に大きな気温上昇はなかったことを示しています。
シベリア、カナダの項での説明と同じで、“20世紀後半のかつてない気温上昇”も、“水蒸気ポジティブフィードバック機構が働いた形跡”も見られません。
(北極の海氷がなくなるという話)
CO2温暖化論では、氷アルベドフィードバックにより北極の気温が上がり、氷の溶解が進んで海面上昇につながると騒がれてきました。そして、アル・ゴア氏は「不都合な真実」の中で、15ページにわたって北極海の衛星画像や潜水艦での観察などを引き合いに出し、CO2増加によって北極海氷は40%減少したとして北極崩壊の悪夢を語りました。
ゴアの本に出てきたシロクマの話も有名になりました。
こんな話の根拠の一つになっていたのが、下図2のような衛星観測による北極海表面積の推移でした。図2の縦軸は海氷面積、横軸は1年の季節推移です。2002年から2010年まで、各年ごとの変化が示されています。海氷面積は、毎年、5月頃から減少し始め9月頃に最低になり、その後冬に向かって拡大して3月頃に最大になります。
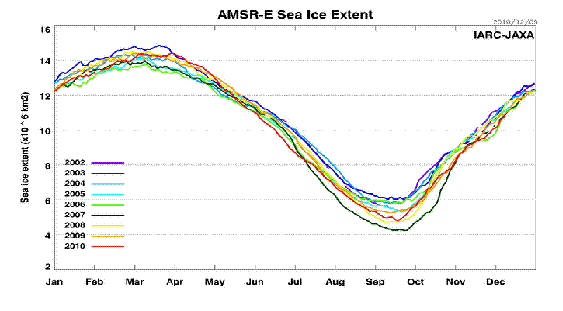
図2 北極の海氷面積の変化(WUWTより抜粋して引用) |
9月の最小面積の所をみると、2003年(紺色の線)から2007年(緑色の線)まで、次第に減少しました。そしてアルゴア氏の本が出版されたのもこうした時期でした。
しかしながら、その後、2008年、2009年と海氷面積は回復拡大してきています。
北極海氷の大幅減少は、1920年から1940年頃にも見られ、当時も大騒ぎになりました。当時の話は既に多くの人が本や論文で紹介しているので省略します。
歴史的事実を振り返ろうともせず、地球上での短期変動に大騒ぎするのは、気候変動の本質を見誤る元と言えるでしょう。
(北極気候は、海洋活動の影響が大きい)
アラスカ大学名誉教授でオーロラ研究権威の赤祖父俊一氏は、2007年に出版された「正しく知る地球温暖化」(誠文堂新光社)の中で、次のように述べておられます。
『北極海氷は、昔から拡大と減少を繰り返している。北極海氷の減少原因は、北大西洋の暖かい海水の流れ込みが原因である。これは北大西洋振動(AMO)という数十年の周期で起こる自然現象である。こうした振動は、北極の低気圧が周期的に変動する北極振動が原因である。これが強くなると南方から極に向かって暖かい風が吹き込み、暖かい海流が北極圏に流入する。その結果、欧州、シベリア、米国東部などは温暖化し、北極圏の海氷が減少する。』
『北極圏でおきている現象(温暖化、海氷の融解、氷河の減少)は、これまでも繰り返されたことであって20世紀後半だけの現象ではない。2007年、夏、北大西洋海水温度は低下し始めている。海水による北極海の氷の溶解はいずれ止るのでは。』
実際、北極海氷にかかる現象は、赤祖父氏の推測通りに推移しているようです。
他にも有力な海洋影響説があります。カムチャッカとアラスカの間にあるベーリング海峡を通して太平洋の暖かい海水流入が北極海氷減少や周辺温度上昇をもたらしている、とするものです。ワシントン大学R.A.Woodgate氏等による論文*も、そうした説の一つです。
R.A.Woodgate et al.“The 2007 Bering Oceanic Heat Flux and anomalous Arctic
Sea-ice Retreat“ Geophysical Research Letters,37, L01602 (2009)
彼らは、1990年から海峡の3ケ所での海水温度測定と衛星による海面温度測定データから、海水輸送量と熱輸送量を推定しています。海水は、時期によって北向き(北極向け)が大となったりその逆になったりします。
2007年は、北向きの海水輸送量も熱輸送量も最大で、2001年から2007年にかけて北向きの熱輸送量は倍増しました。その熱量は北極チュクチ海に入射する太陽エネルギーの1年分に相当し、2007年の海氷融解分の3分の一に相当すると推定しています。こうした結論は、上記図2において、2007年の海氷面積が最小になったことを裏づけています。論文では他にもいろいろな考察がされていますが、割愛します。
北極気候変化の原因は海流の影響だったようです。北極気候変化に関して、CO2原因説に固執することも、根拠の不確かな恐怖話に振り回されるのも、もう止める時期がきていると思います。
|
2010年12月9日(木)
2009年11月、世界を驚愕させ、後に「クライメートゲート事件」と命名された事件が発生してから1年少し経過しました。今日はこの事件を振り返ってみます。
(事件の発生)
2009年11月17日、国連の下部組織、気候変動にかかる政府間パネル(IPCC)を支えてきた英国イーストアングリア大学の気候研究所(CRU)のコンピュータから、IPCCのリーダー科学者達が交信していた1000通を超えるメールと多量の文書が引き出され、米国のブログサイトに掲載されるという事件が勃発しました。
CRUは、国連が推進してきたCO2温暖化論の中心研究拠点の一つでした。
流出情報にはは次のような実行者の「口上書き」が付いていました。
『気候科学がこれほど大きな問題になった現在、もはや隠してはおけない。ランダムに選んだ交信メールとコード(演算プログラム)、文書を公開する。気候科学の実態と、背後にいる人間の素顔を伝えるだろう。アップは短い。ただちにダウンロードされたし。』
流出情報は、衝撃的内容 を含んでいました。IPCCのリーダー科学者達が、自分たちの主張を正当化するために、「気候データの恣意的加工、改ざんや秘匿、論文誌への圧力による反対派論文の掲載妨害、等々、数々の不正行為をやっていた」ことを示唆する内容だったのです。そしてブログサイトの投稿者の一人がウォーターゲート事件に擬えて、“クライメートゲート事件”と名づけました。
2009年12月、米国のモシャー(Steven Mosher)とフラー(Thomas Fuller)の両氏は、この事件を『CLIMATEGATE THE CRUTAPE LETTERS』として1冊の本にまとめ出版しました。この本は、2010年6月初め、東京大学生産技術研究所の渡辺正教授によって翻訳されて、『地球温暖化スキャンダル 2009年秋:クライメートゲート事件の激震』(日本評論社)の表題で出版されています(以下では、この本を『地球温暖化スキャンダル』と呼称します)。
事件の当事者達がいた欧米では、その後もおびただしい量の事件関連情報が発信され、メディア、政官界、企業、科学者社会を巻き込んで大騒ぎになったようです。前述の渡辺教授は、雑誌「化学」の2010年3月号、5月号に、事件後の推移を判りやすく整理されています。
(事件の本質は何だったのか)
情報をネットに流出させた当事者は、なぜ、米国のブログサイトを選んだのでしょうか。それは、IPCCのCO2温暖化論に異議を唱えてきた人達が、主に米国ブログサイトを拠点にして活動していたからでした。
『地球温暖化スキャンダル』を読むとよくわかりますが、IPCCに依拠し、CO2温暖化論を唱えてきた科学者達は、これに異議を発する人々を“懐疑派”と呼び、徹底して忌み嫌っていました。クライメートゲート事件は、その懐疑派の拠点であった二つの小さなブログサイトとその運営者がもたらしたこと、と言っても過言でないでしょう。
一つはカナダのスティ−ブ・マッキンタイヤ氏が運営するCA(ClimateAudit)、他の一つは、米国のアンソニー・ワッツ氏のWUWT(Waats Up With That?)でした。
マッキンタイヤ氏とその仲間は、IPCCのCO2温暖化論の根幹だった以下の論文に関して、元データ開示を要求して10年以上にわたって追及し続けていました。
1)1990年の都市温暖化にかかるフィル・ジョーンズ論文
2)ペンシルベニア州立大教授、マイケル・マンのホッケースティック論文
3)CRU副所長キース・ブリッファの同様のホッケースティック論文
一方、ワッツ氏とその仲間は、ボランティアを動員して米国の気温観測点状況の実地調査を行い劣悪な観測点環境をブログWUWT上で、次から次と公開してきました。今や、ブログWUWTは月200万アクセスがある人気ブログになり影響力を増しているようです。
『地球温暖化スキャンダル』によれば、懐疑派は、米国および英国の情報公開法を盾にとって基礎データや元データを要求しましたが、IPCCのリーダー科学者や当局は、様々な言い訳を繰り返して開示を拒絶し続ける一方で、不都合な論文の締め出しを図り、学術雑誌への圧力をかけるなどの不誠実な行為を繰り返し、あろうことか基礎データの一部を消し去っていたのでした。
『地球温暖化スキャンダル』の著者モシャーとフラーの両氏は、ブログCAやWUWTの読者で、マッキンタイヤやワッツ達“懐疑派”の考え方や行動はもとより、IPCC派リーダー科学者達の表向きの対応、両派のやり取りの経過などを熟知していたはずです。
そんな彼らが流出情報を入手したことで、IPCC派リーダー科学者達の行動の背後の意図や策略が明らかになり、“裏”と“表”がつながったのでないでしょうか。
この本をよめばわかるように、IPCCの主張の根幹部分は、マッキンタイヤ達の執拗な追及によって、事件発生前から破綻同然だった ように思えます。事件は、IPCCリーダー科学者達の不正行為や言説を公開することで、“止めを刺す”役割を演じたということでないでしょうか。
(“そもそも”から変だった)
『地球温暖化スキャンダル』の中で、次のような経緯が紹介されています。
『1979年、国連世界気象機関(WMO)が第1回世界気象会議を開催した。この場において、「拡大中の人間活動が地域の気象ばかりか、地球全体の気候も変える」と断じ、「気候が今後どう変わるか調べ、成果を人類社会の未来に生かそう」とまとめられた。
そして、世界気候会議は「人類を脅かす人為的な気候変動の予測と防止のために」万国の協調を呼びかけ、その後の30年間、気候変動の「予測」と「防止」がキーワードとなる。
1985年、WMOの会議は更に踏み込んだ。「大気中に増加する温室効果ガスが、21世紀前半に前代未聞の勢いで地球を暖める」と断定したのだ。そして、1987年には、WMOと国連環境計画(UNEP)は、気候変動の科学的理解と防止に焦点をあてた世界全体の仕組みが不可欠とし、翌年に、気候変動のかかる国際パネル(IPCC)が発足した。』
1980年代は、気候変動、とりわけ、CO2温暖化に関する基礎データはあまりない状態だったはずです。科学者達の合意もあったとは言えません。なのに、なぜ、こんな結論が出せたのでしょうか。始めにCO2の脅威ありき、だったということなのでしょうか。
国連は、CO2を“やりだま”にあげ、『20世紀後半のかってない気温上昇』という話を作り上げ、世界を一つの方向に持ってゆこうとした、という見方もできます。
事件の流出情報中に、CRUの処理担当ハリー君の次のようなメモがありました。
『・・データベースがひどい。ダミーの観測点ペアが数千とはいわないまでも数百はあり、・・たいてい重複だし観測点の名も座標も同じ、新旧の観測点だろうが、そうなら、なぜこれほどの重複があるのか?。もういやだ。』
これは、IPCC報告書の基礎データを提供していたCRUの気温データがとんでもなくひどい状態だと告発している内容です。
本ブログでも、これまで11回にわたって世界地上気温データを紹介してきました。
20世紀の気温データは、データ管理組織による作為的操作によって歪な姿に変質してしまっていた可能性があります。そして、世界地上気温の実態は、IPCC報告書の内容とはかなり乖離しているようです。
IPCCが主張してきた『20世紀後半のかってない気温上昇』という話は、事実とはかなり異なるように思えます。このことは、また、『大気中CO2増加が原因で20世紀後半に急速な気温上昇があった』とするIPCCの論理にも、大いなる疑念が生じているということになります。
(こんなことでいいのだろうか)
2010年になって、事件当事者達の所属組織や学会組織による事件の調査・検証報告書、国連が委託した国際的科学組織による検証報告等が提出されました。こうした報告書は環境省HPに日本語版も掲載されています。いずれも、IPCC組織や行動のあり方について課題や問題点を指摘したものの、なんとなく適当なところでお茶をにごした、という印象はぬぐいきれません。
欧米では、主要な新聞、TVなどメディアが事件を繰り返し大きく取り上げ、議会も責任追及と実態調査が続いています。CO2 温暖化論は、“人類史上最悪の科学スキャンダル”とか“温暖化詐欺”といった言葉も飛び交う中、様々なスキャンダルが次から次に見つかり、これらをすべて含めるIPCC Gatesなる言葉も有名になりました。いまや、CO2温暖化論の見直し論、IPCC解体論の声も、大きくなっているように感じます。
一方、日本では、事件発生当時から世の中での扱いは小さく、この事件に大きな注目が集まる動きもなく推移し、今では何事もなかったかのように“異様に静か”です。
もしかしたら、IPCCの言う 『20世紀後半のかってない高温化』とは“彼ら自身の自作自演”だった、という重大なる疑念(疑惑と呼ぶべきかもしれません)が生じているにもかかわらず、日本では“地球温暖化”という言葉が当然の事実であるように、報道されています。
最近の新聞報道によれば、環境省は地球温暖化法案にかかる基本方針として、1990年比でのCO2発生量の内の10%位は排出権購入を考える、といった記事も出ていました。そしてCOP16に関連して、CO2削減対策を地球温暖化法案どう盛り込むか、といった議論が盛んです。
しかしながら、かってない高温化が事実でないなら、CO2を削減する必然性も使命感もなくなるはず です。なぜなら、“CO2の所為で地球が高温化するから”が削減取組みの正当性を担保する論理だったからです。
今の状況は、CO2温暖化論にかかるこうした根本的問題が眼前に提起されているということなのです。日本のメディア、政治家、官僚、評論家、科学者の皆さんは、何の疑問も感じておられないのでしょうか。
今の姿は、“異様な国、日本”と呼ぶべき状況のように思えます。
次回から、また、おかしな世界気温データの紹介をします。
|
2010年12月6日(月)
IPCCの言う「“寒いところは気温が上がり易い”は、ほんとうだったのか」の検証の第4回目として、アラスカの気温データについて紹介します。
図1は、IPCCの第四次報告書『自然科学的根拠』分冊掲載、Fig9.12から取り出したアラスカの気温推移の拡大図です。
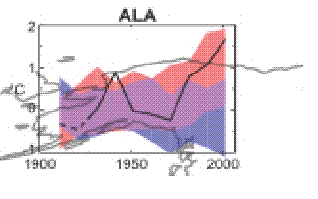
図1 IPCC報告書に掲載されたアラスカの気温推移
(縦軸は、これまで説明と同様に平均値との差異で、℃表示) |
20世紀後半の気温上昇(黒線)は顕著で、1970年頃から2000年までに2℃弱上昇したことになっています。こんな推移は本当だったかのか、というのが本日のテーマになります。比較対象に、二つの異なるソースのアラスカの気温推移を示します。
図2は、AnthonyWatts、JosephD’Aleoの『SURFACE TEMPERATURE RECORDS:POLICY-DRIVEN DECEPTION?、』SPPI ORIGINAL PAPERから引用した図です。R.A.Keen という人の論文(*1)が元データで、Central Alaska Inventory and Monitoring Network(CAKN) というデータセットに基づいています。
(*1)http://science.nature.nps.gov/im/units/cakn/Documents/2008reports/
CAKN_Climate_Data_%20Analysis_%20Keen_2008.pdf.
北緯60度から65度、西経140度から155度の地域における9基の観測点データが使用され、1900年から2004年までの推移が示されています。
(但し、縦軸偏差については記述がない)
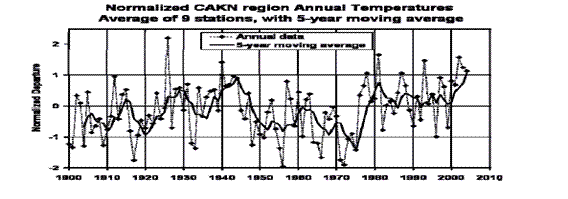
図2 CAKNによるアラスカの気温推移 |
11月25日のNO8で紹介した北欧NORDKLIMのデータとかなりよく似ていて、
1940年頃に最大のピークがあり、1980年以降に少し小さいピークがあります。
Keen氏は、上記のデータとNOAA GHCNのアラスカの気温データとを比較しました(図3、図4)。両者の気温トレンドの差異は顕著で以下のようでした。
CAKN 0.69℃/100年、 GHCN 2.83℃/100年
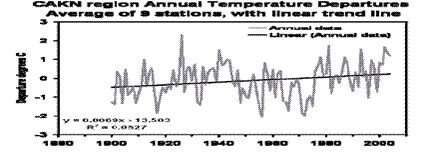
図3 CAKNデータ |
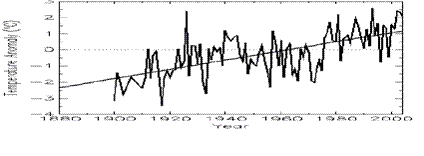
図4 NOAAのGHCNのアラスカ気温データ |
CAKNデータに比べて、NOAAのGHCNデータは、異様なほどに20世紀後半の気温上昇が強調されていることが判ります。 基礎データをNOAAに頼るIPCC報告書において、図1のような図が掲載されたのも、当然なのかもしれません。
下図5は、アラスカ大学の気候研究センターが2009年3月9日に発表している記事
“Temperature Change in Alaska”(*2)からの引用データです。
(*2)http://climate.gi.alaska.edu/ClimTrends/Charge/TempChange.html
観測点として、アラスカ全体で15地点が選択されていて、CAKNよりは、より全体像を表していると思われます。縦軸は平均値からの差異ですが基準は示されていません。
基準が異なるため数字自体は違っていますが、1949年以降の気温の相対的推移は、図2とほぼ同じです。
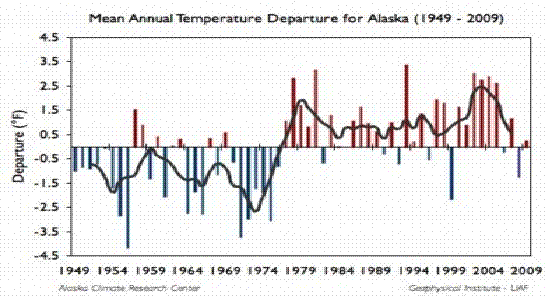
図5 アラスカ大学の発表データ |
図5については、同じ研究グループが以下の論文(*3)を発表しています。
(*3)B.Hartmann,G.Wendler, “The Significance of the 1976 Pacific Climate Shift in
The Climatology of Alaska” J.of Climate vol18,15 Nov 2005,
研究者達は、図5の推移に関してトレンド直線を引くのは間違いで、図5は1977年頃を境にして、太平洋10年規模振動PDO(Pacific Decadal Oscillation)(下図6)の位相が変化したことによる気温ジャンプだ、としています。
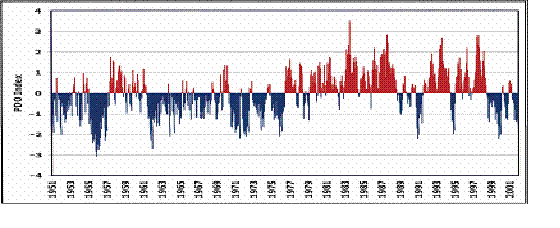
図6 PDO指数の変化(赤と青で位相が逆になる) |
いずれにしても、アラスカにおいても、「“寒い地域の気温は上がり易い”も“水蒸気ポジティブフィードバックが働く”も、事実とは異なる」ということだったのでしょう。
|
2010年12月2日(木)
前回に引き続き、カナダ、ロシア(シベリア)の気温推移について説明します。
前回引用したE.M.Smith氏の論文には、NOAAの気温データセットGHCNの採用観測点推移も掲載されています。それによると、1900年〜2005年のカナダ、シベリアの採用観測点数は、図1のように推移していました。
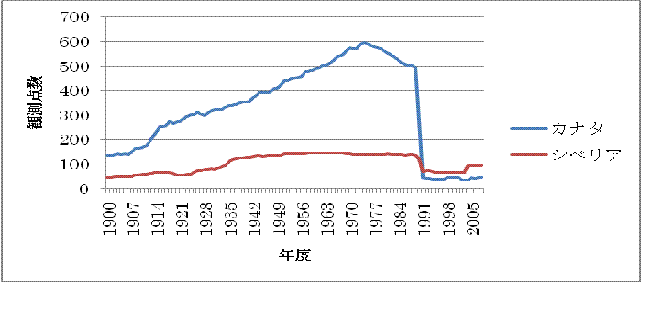
図1 カナダ、シベリアの採用観測点の推移 |
カナダの観測点数は、かつては500を越えていたのに、1990年頃に急速に減少し、今では30程度にまで間引きされています。
シベリアも同じ時期に半数程度に減り、2003年頃から数十の地点が追加されました。
図2および図3は、カナダにおけるGHCN採用観測点の場所を示す分布図です。
1975年と2009年とが比較されています。両図で、観測点は人口数などで区分されており、赤色は都市部、橙色は都市郊外、緑色は田舎の観測点となっています。
そして、◇印が採用観測点(その年の気温計算に使用された観測点)になります。
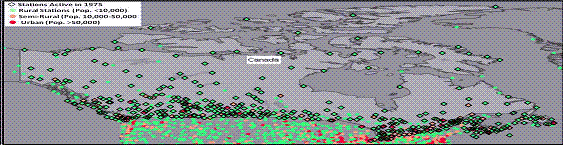
図2 1975年時点におけるカナダのGHCN採用観測点の分布 |
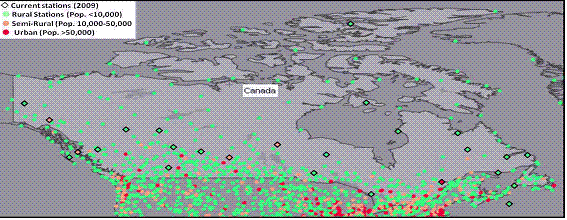
図3 2009年におけるカナダのGHCN採用観測点の分布 |
1975年当時、主に米国との国境線にそって多数観測点があったのが、2009年には劇的に減少している様子がよくわかります。とりわけ顕著なのは、北方地域の観測点がほとんどなくなっていることです(北緯65以北では1基だけ)。
二つの図から、ワッツ達が、“カナダでは北の方の気温が上がっていない観測点が除去され、その代わりに南の方の気温上昇が大きなデータが適用された”と解析したことがよく理解できます。
一方、図4は2009年時点でのシベリアの観測点分布です。
赤色は2003年から2009年に追加された採用観測点、青色はこの時期に間引きされた観測点です。黄色のX印は2003年以前から続いている採用観測点を意味します。
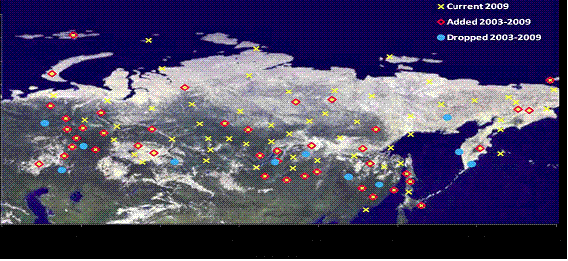
図4 2009年におけるシベリアのGHCN採用観測点の分布 |
ここでも南方の観測点数に比べて北方地域の観測点は圧倒的に少ないことが判ります。北方では、緯度、経度で区分する格子点において観測点の欠落が生じていたはずです。
そして、観測点のないところには他地点データが適用され、おそらくは、南の方の高温地点のデータが使用されたと推測されます。
またこの図は、2003年以降に追加されたのが、主に南方の(気温が高い)観測点だったことも示しています。前回の気温推移(NO9の図1)では、この頃から平均気温が少し上がっていることと関連していると思われます。
前回説明したように、CO2温暖化論では氷アルベドフィードバック機構という中核的論理に基づいて、北の地域の気温が上がり易いとされ、CO2増大がその引き金になるとされてきました。IPCC報告書における気候モデルにもとづくコンピュータシミュレーションによる20世紀気温推移の再現も、21世紀の気温変化予測も、こうした理屈が存分に応用されたはずです。
いわば、北の寒いところは、IPCCのCO2温暖化論の中核思想を証明する“虎の子の地域”でした。しかしながら、NO8で説明した北欧の場合も、NO9、NO10で説明したカナダ、シベリアの場合もそうであったように、そんな地域の気温データが、じつはぞんざいに扱われ、あろうことか、実データでなく、南方データで代替されていたという疑い(事実に近い)が高まったのです。
次回では、虎の子地域の一つ、アラスカの気温データについて説明します。
|
2010年11月29日(月)
「“寒いところは気温が上がり易い”は、ほんとうだったのか」の第二弾として、カナダ、ロシア(シベリア)の気温推移について紹介します。
図1は、NOAAの世界気温データGHCNに掲載されている、カナダ、シベリアにおける20世紀以降の気温生データ(各年平均値)を示しています。
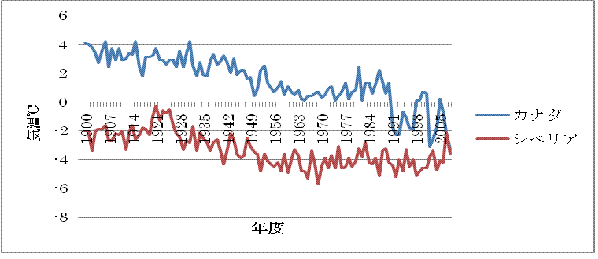 図1 カナダ、シベリアの気温生データの推移 図1 カナダ、シベリアの気温生データの推移 |
縦軸は実測気温値℃。左端は1900年、右端2008年
E.M.Smith氏の以下の文献データより引用して作成。 http://chiefio.worldpress.com/2009/10/27/ghcn-up-north-blame-canada-comrade/
一方、図2は、NO7でも示したIPCCの2007年第四次報告書掲載の世界気温推移図から、シベリア部分を抽出・拡大したものです。
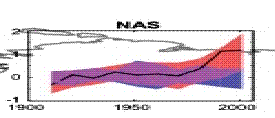
図2 IPCC第四次報告書掲載のシベリアの気温推移
(縦軸は1900年から1950年までの世界平均値との差異を℃で表示) |
二つの図の違いは顕著です。生データの図1では、両地域ともに、20世紀以降において継続的に気温低下があったことを示しています。一方、IPCCデータの図2では、シベリアは20世紀後半に約1℃も急激に気温上昇したことになっています。
図2は、英国気象庁ハドレー気候センター(Hadley Centre)のデータを英国イーストアングリア大学(UEA)気候研究所(CRU)が解析しているHadCRUTEMPというデータセットに基づいています。厳密には図1と図2はソースが異なりますが、NO4で説明したようにCRUはデータの大半をGHCNに依存してきました。従って、図2は、データソースの違いの差というよりCRUによる補正の結果と考えるべきでしょう。
それにしても、なぜこんなに異なる図になるのでしょうか。
こうした疑問に対する答えのような事件が起きていました。2009年11月17日のクライメートゲート事件発生の約1ケ月後、2009年12月15日、モスクワの経済分析研究所は、CRUに対して次のような抗議をしていました。
『ロシアから英国ハドレーセンターに送った気温データ中、CRUは20世紀後半に昇温した観測点(全体の25%)のデータだけ使って解析し、残りの75%を無視した。その結果、世界の地上面積の約12%を占めるロシア気温データが、40%程度しか世界気温算出に正確に反映されていない。そして、CRUが無視した地点の平均温度は、20世紀後半も21世紀も、ほとんど気温は上がっていない。』
IPCC報告書におけるシベリアのデータは、“20世紀の後半にCO2が増加した結果として異常に温度が上がった”としてきたIPCCの言い分を“証明”するために、CRUによってあやしげな操作が行われたことを示しているように思えます。
一方、カナダについては、上記のIPCC報告書で米国気温と一緒にされていて単独データがありません。但し、既に紹介したワッツの文献に以下の既述があります。
“ Canada’s semi-permanent depicted warmth comes from interpolating from more southerly locations to fill northerly vacant grid boxes, even as a simple average of the available stations shows an apparent cooling.”
“SURFACE TEMPERATURE RECORDS:POLICY-DRIVEN DECEPTION?”
SPPI ORIGINAL PAPER、 http://scienceandpublicpolicy.org/images/ stories/ papers/originals/surface_temp.pdf
ワッツのコメントでは、“気温算出に利用可能な観測点の平均気温数字は、明らかに気温低下を示しているのに、(カナダ気象庁の公式発表)データでは、半永久的に温暖化を示している”。“カナダの温暖化は、(気温が上がっていない故にデータを除去した)北の方の空の格子点に、南の方の(気温上昇が大きな)データを適用したからだ”と解析しています。( )内は筆者補足
図1は、地球の地上面積全体のかなりの部分を占め、北の寒い地域の大部分を占める両地域で、20世紀の気温推移は 温暖化どころか寒冷化していたこと を示しており、“寒いところは気温が上がり易い”を明らかに否定しています。
図1は、また、CO2温暖化論を語るにあたってもっと重大なことを示しています。
CO2温暖化論の中核思想の一つ、アルベド・フィードバック理論への大いなる疑問を提起しているからです。
CO2温暖化論で“寒いところは気温が上がり易い”結果として、気温はこの100年間で、北緯60度以北では約3℃上昇し、北緯20度以南では0.5℃程度、これらの中間地域では1.5℃程度上昇した、という説明がされていました。
単純にCO2による温室効果による気温上昇であれば、ベース気温の値にかかわらず同じように上昇するはずです。しかし寒いところでは、氷アルベド・フィードバック機構が働くとされたのです。
これは、『CO2が増加して温度が上がれば、アルベド*の大きい氷が解けて、アルベドの小さい地面や海面が露出する結果、吸熱が大きくなり、水蒸気が増える。そして、その水蒸気の大きな温室ガス効果により、さらなる温度上昇が起きる。これが繰り返されて温度上昇が増幅される』という理屈でした。
*アルベドとは太陽光の反射率を示す指標で、森林3〜15%、畑15〜25%、土10〜40%(水分で変わる)、雪40〜90%(汚れで変わる)、新雪75〜95、氷30〜40%、水5〜25%、草地10〜30%、厚い雲(層雲)60〜90%、薄い雲30〜50%、砂地15〜45%、などとされる。地球平均では通常、30%を使用することが多い。
氷アルベド・フィードバック機構は、北極、グリーンランド、南極などの氷の減少や、シベリア、カナダ、アラスカの永久凍土帯の融解に大きく影響する、とされてきました。
そして、この機構は、また、“21世紀において寒い国を中心に恐ろしい気温上昇に直面する”と人々を恐怖に陥れた将来予測の中核をなす理屈でもあったのです。
しかし、シベリア、カナダの寒い両地域でも、気温は上昇していなかったようです。
現実はこうした理屈とは、あまりにも違っていたということなのでしょう。
(NO9 終わり)
|
2010年11月25日(木)
今回から数回にわたり、IPCCの言ってきた「“寒いところは気温が上がり易い”は、ほんとうだったのか」という視点から、北欧、カナダ、ロシア(シベリア)、北極、南極、グリーンランドなど、寒い地域の気温推移について、紹介します。
北欧の気温推移について
クライメートゲート事件の興奮さめ止まぬ2009年11月29日、エッシェンバック(W.Eschenbach)と言う人が、流出メールにあるスウェーデンのカルレン教授とIPCC科学者達とのやりとりを取り上げ、ブログWUWTに投稿しています。
問題になっていたのは、IPCCの第四次報告書に掲載された北欧の気温変化を示す下図(NEUと記された部分)でした。
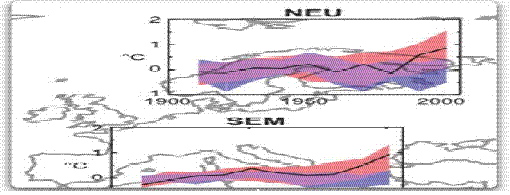
図1 2007年IPCC第四次報告書掲載の北欧の気温推移の拡大図(NEU) |
図1で黒線は、地上の実測気温推移、灰色と赤色の帯は気候モデルによるコンピュータシミュレーション結果で灰色の帯は自然変動(太陽活動および火山活動)のみ考慮した時、赤色の帯は自然活動+人為的活動(主にCO2の影響)を考慮した時、としています。
気温値は 英国ハドレーセンターとCRUが編集しているHadCRUTEMPから取られ、1900年〜1950年までの世界平均との差異(anomaly)を℃で表示しています。
この図では、大体1980年ぐらいまでは、それほど大きな変化がなかったのに、その後、急激に気温上昇(2000年までに約1℃上昇)したことになっています。
これに対して、カルレン教授は、気候問題にかかる北欧諸国の共同プロジェクトであるNORDKLIMの気温データでは、北欧の20世紀の気温推移(生データ)は、次ページの図2のようだったと指摘して、何が違うのかと問いただしたのです。
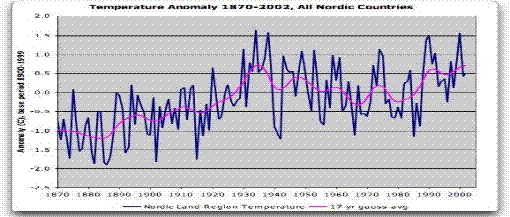
図2 NORDKLIM気温データから構成した北欧の気温推移(エッシェンバック氏) |
青線は各年の地上気温生データの推移、ピンク色の線は17年間の平均値の推移を示し、縦軸は1900年から1999年の平均値との差(anomaly)で、℃で表示されています。
カルレン教授は、NORDKLIMの気温データでは、『1930年から1940年にかけて1℃程度上昇した大きなピークがあり、20世紀後半には、それより少し低い、0.5℃程度上昇しているピークがあった。一方、IPCCデータでは、1940年頃は平坦に推移し、20世紀後半において、1℃もの急速な気温上昇となっている』と指摘したのです。
エッシェンバック氏は、IPCCのトレンバース氏(K.Trenberth)およびジョーンズ氏(Fil Jones)とカルレン教授との交信メール内容を具体的に検証して、IPCC派の科学者達が、いい加減な応対をし、時にウソの返答をしていることを鋭く指摘しています。
HadCRUTEMPは、基礎データをCRUが補正して構成されています。図1はどのような基礎データ(おそらくNOAAの元データ)を使用し、どのような補正をして出来たのかはわかっていないようですが、不可思議な補正の結果と言えるのでないでしょうか。
いずれにしても、NORDKLIMの気温データ(図2)は、極めて重要なことを示しています。IPCCは、第四次報告書において“20世紀の後半に人類が排出するCO2が急速に増大した結果、気温が急激に上昇していた、そして、それは世界中のどこでもそうだった”という結論を導出しました。
しかしながら、北欧の生データによる気温推移は、明らかにIPCCの結論を否定するものだったのです。そして「寒いところは気温が上がり易い」も、北欧データには当てはまらないことを示しています。(NO8終わり)
|
2010年11月22日(月)
米国気象予報士ワッツ(Anthony Watts)が運営するブログWUWT(Waats Up With That? http://waatsupwiththat.com-Waats
Up With That?)の2010年11月8日版に、炭素取引に関する重大なニュースが発表されていたので、それをまず紹介します。
“Public carbon trading dead in the USA”という表題になっており、シカゴ炭素取引市場(The Chicago Carbon Exchange: CCX)の閉鎖を伝えています。内容は、Suite101.comというブログに掲載されたJ.O‘Sullivanという人が書いた ”Carbon Trade Ends on Quiet Death of Chicago Climate Exchange“*の紹介です。
*http://www.suite101.com/content/carbon-trade-ends-on-quiet-
death-of-chicago-climate-exchange-a305704#ixzz14wnNPJ8D
それによると、CCXは2000年11月に設立されました。ノースウェスタン大学のRichard Sandor教授という人が、シカゴを拠点とする財団で、オバマ大統領もボードメンバーであるJoyce Foundationから約100万ドルの資金を得て始めたと書かれています。
CCXは2010年10月21日に、2010年内に炭素取引を終了させるとアナウンスしたのですが、主要メディアはこのことを伝えていないと書いています。日本の主要メディアもこのニュースは報道していないのでないかと思います。
CCXは、2003年の営業開始以来、フォード、バンカメ、IBM、インテルなど有力企業が参画し、将来、5000億ドルから10兆ドルの巨大市場に発展するという予測もされていたようですが、10年弱で静かに消えることになるようです。
サリバン氏は、欧州の同様の組織 The Europian Climate Exchange (ECX)についても、京都議定書に替る仕組みが導入されないと同じ運命を辿るのでないかと書いています。
アル・ゴア氏やIPCC現議長パチャウリ氏はCCXを強力に後押し、ゴア氏が炭素取引で多額の利益を得ていたことは有名になりました。そんなCCXの崩壊は、国際的炭素取引の“静かな死”の始まりとなるのでしょうか。いずれにしても、CO2温暖化論を巡る環境が大きく転換し始めた象徴的事象と言えるのかも知れません。
*******************************
世界気温データの話に戻ります。IPCCの2007年第四次報告書に、次ページの図1が掲載されました。これは見にくいので北欧部分の拡大図を図2に示します。
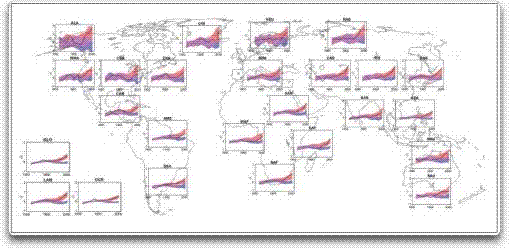
図1 IPCC第四次報告書『自然科学的根拠』分冊 Fig9.12 |
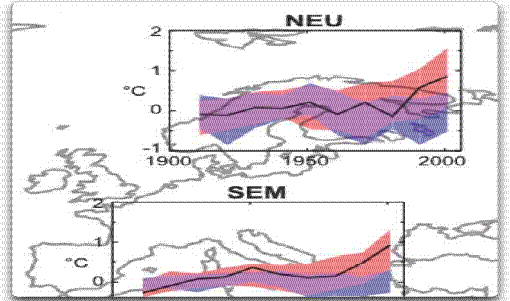
図2 図1の北欧(NEU)の拡大図 |
上図は、1906年から2000年までの地域別の地上の実測気温推移(黒線)および気候モデルによるコンピュータシミュレーション結果*を示しています。
*灰色の帯は自然変動(太陽活動および火山活動)のみ考慮、赤色の帯は自然活動+人為的活動(主にCO2の影響)を考慮。
気温値は1900年から1950年までの世界平均との差異を℃で表しており、英国のハドレーセンターとイーストアングリア大学気候研究所(CRU)が編集しているデータセット HadCRUTEMP がベースになっています(元データの多くはNOAAのNCDC)。
特徴的なことは、全ての地域において1970年〜1980年頃から、急速に気温上昇があった、としたこと、シミュレーションでそれを再現した(赤帯)、としたことです。
IPCCはこの報告書をもって、「CO2が原因で20世紀後半にかつてないほどに気温が上昇した」と結論し、更に、「気候変動についての科学的議論は終わった。いまや、政策者の出番である」と宣言したのでした。
そしてIPCCは世界中にCO2削減を速やかに実施するように求め、日本でもIPCCに関わった科学者達による緊急声明などというものが提起されています。そして環境省を中心にして、「STOP THE 温暖化」プロジェクトなど、様々な施策が進められ、地球温暖化阻止一色になっていったのでした。
振り返れば2007年頃は、IPCCの権威と名声が頂点に達した時期だったのでしょう。地球温暖化問題への貢献大として、アル・ゴア氏とIPCCはノーベル平和賞も受賞したのでした。しかし、この報告書以降、CO2温暖化論とIPCCに対し痛烈な批判が続出し始めたのです。
2008年、スウェーデンのカルレン教授(W.Karlen)は、IPCCのリーダー2名、米国立大気研究センター(NCAR)のトレンバース氏(K.Trenberth)とCRU所長ジョーンズ氏(Fil
Jones)に対して、「気候問題にかかる北欧諸国のJoint Project NORDKLIMの気温データからは、IPCCが出した20世紀後半における急速な気温上昇は見出せない。どこからこんな数値が出たのか」と問いただしました。トレンバース、ジョーンズ両氏とカルレン教授のやり取りの詳細が、クラーメートゲート事件の流出メールに入っています。
2009年、本欄NO4で紹介したE.M.Smith氏は、NOAAのGHCNについて、カナダやシベリアの気温生データは、IPCCの言い分とは大違いで、20世紀を通して次第に低下していたと発表しました。
事件勃発直後の2009年11月25日、ニュージーランド気候科学連合の関係者が、ニュージーランド国立水圏気圏研究所(NIWA)が発表した公式データにクレームをつけました。公式データでは、IPCCと同様に20世紀後半に急激に温度上昇している図になっているのですが、NZの気温生データにはこのような急な昇温傾向はなく、20世紀を通して小さな変動を繰り返していただけだったのです。
2009年12月15日、モスクワの経済分析研究所は、「ロシアから英国ハドレーセンターに送った気温データ中、CRUは20世紀後半に昇温した観測点(全体の25%)のデータだけ使って解析し、残りの75%を無視した。残りの地点の平均温度は、20世紀後半も21世紀も、ほとんど気温は上がっていない」として、CRUに抗議しました。
その後、欧州、中国、豪州、アラスカ、北米のIPCCデータについてもおかしいとの批判が出されていて、今や、IPCCの第四次報告書データに対して、根本的な疑念が浮かんできています。次回以降で、具体的に説明します。(NO7終わり)
|
2010年11月18日(木)
前2回において、世界気温の元締めNOAAのNCDCが管理する、世界気温データネットワークGHCNの状況を説明しました。そして、“1990年以降において世界気温が異常に上昇した”とされてきたのは、ほんとうに気温上昇があったからでなく、NOAAが、気温算出に際して、低い気温を示していた観測点データを減らし(間引きし)、その代わりに、高温を示す他の地点の気温データで代替したことによって起こった“人為的温暖化”だったのでは、という指摘があることを紹介しました。
今日は、気温データの補正について説明します。
各国から収集された気温データ(生データ)は、一般に、高度の違い、局所的な気象環境の違い、測定器の違いなどの固有の条件によって影響されています。従って、世界平均気温を算出するために、こうした生のデータを補正し均質化する、とされていました。
しかしながら、世界気温データを公表してきた英国のCRU、米国のNASAとNOAAのいずれも、最近まで、どんな補正をしたかは外部に一切公表していませんでした。そして、クライメートゲート事件後、とんでもない補正の事実が次々と見つかったのです。
元NASAの物理学専門家E.R.ロング(Edward R Long)は、NOAAの米国についての気温データセットである USHCN―V2 に関して次のような調査をしました。米国本土の48州で、都市および都市近辺の観測点と、田舎の観測点を、それぞれ、一つのステーションずつ選び、観測点の生データとNOAAの補正後データを比較したのです*。
*“Contiguous U.S. Temperature Trends Using NCDC Raw and Adjusted Data for
One-per-State Rural and Urban Station Sets,” SPPI original Paper (27 February 2010)
以下の二つの図には、都市の平均が赤線で、田舎の平均が青線で示されています。
また、縦軸は、各年の気温データと、1961年から1990年までの30年間の平均値との差異(偏差:anomaly)であり、11年の移動平均値として示されています。
生データでは、図1のように、都市と田舎は1965年ぐらいまではほとんど差がなく推移した後、1970年頃から都市温度が上昇して次第に差が開いていきました。
この差は、20世紀後半における都市化推移を端的に示しています。
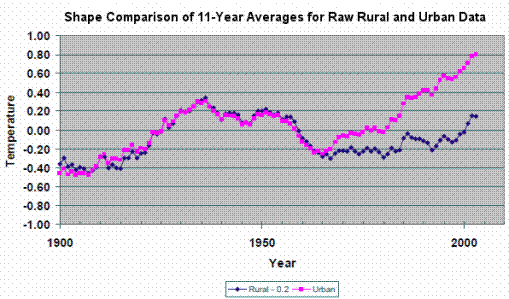
図1 生データによる都市と田舎の比較(赤は都市、青は田舎) |
ところが、NOAAによる補正後データの図2では、田舎と都市との温度差が大きく減少しており、しかも、田舎の温度が、都市の温度に合わせるように補正されていたのです。
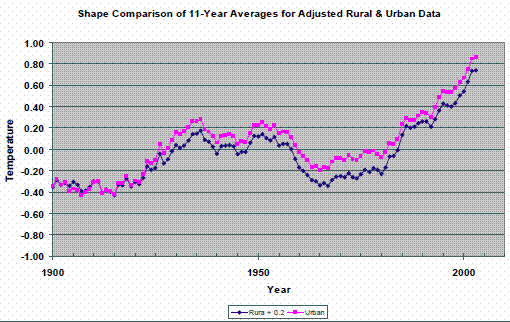
図2 補正後のデータにより都市と田舎の比較(赤は都市、青は田舎) |
NOAAが公表しているデータは、常にこうした補正がされています。この例の場合は、信じられない上方修正がされていたことを表します。NOAAにどんな意図があったかわかりませんが、弁明のしようがない不正な操作のように思われます。
一方でこの図は、米国には、20世紀後半でも温度上昇していない地点が結構存在する、という重要なこと示しています。もし、20世紀後半の温度上昇は、大気中CO2増大が主な原因とするのなら、全米で、概略、一様に温度が上がる、と考えるのが自然です。
事実はかなり異なる、ということなのでしょう。
いずれにしても、こうしたおかしな補正がされていたことは大問題だと思います。
米国の著名な気候学者のひとり、フレッド・シンガー(Fred Singer) は、もし、きちんとした観測点管理と適切なデータ処理が行われていれば、1979年から1997年までの米国の平均気温は、ほとんど上がっていなかったはず、とコメントしていますし、
既に紹介したワッツはD‘Aleとの共著「SURFACE TEMPERATURE RECORDS:POLICY-DRIVEN DECEPTION?」において、20世紀の世界の温度上昇0.7℃の内、50%以上は、間引きとデータコピーが原因と推測しています。
|
2010年11月15日(月)
前回は、世界気温データの元締めだったNOAAのNCDCが管理するGHCNデータにおいて、採用観測点(気温算出に用いる観測点)数の減少(間引き)に反比例するかのように、平均気温は1990年頃から急激に上昇した後、2005年過ぎから再度、上昇していたことを、示しました。
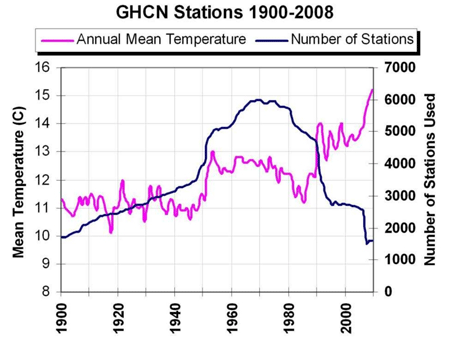
図1 GHCNにおける世界平均気温(赤)と採用観測点数(青)の推移 |
本欄NO2で紹介した、米国のワッツ(Anthony Watts)とカナダのJoseph D‘Aleoは、“SURFACE TEMPERATURE RECORDS:POLICY-DRIVEN DECEPTION?、”
SPPI ORIGINAL PAPER という200ページを越える論文を共著で発表しています。
論文は以下のWEB SITE でも見ることができます。
*http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/surface_temp.pdf
この中で、ワッツ達は、GHCNで間引きされた観測点の実態を調査した結果を、下図2のように分析しています。間引きされた観測点を、田舎(緑)、郊外(赤)、都市(青)で区分して比較すると、田舎の観測点減少が圧倒的に多かったのです。また、この図では示されていないのですが、高緯度地点や高地地点も優先的に削除されていました。
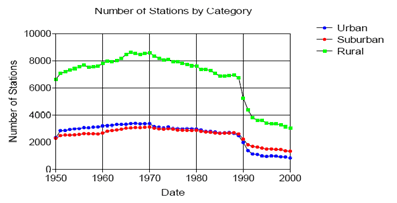
図2 削除された観測点の区分別の数と比率 |
ワッツ達は、削除された観測点の多くは、20世紀を通じて温度上昇が小さいか、横ばいまたは低下している地点であり、残された観測点の多くは、20世紀後半において高温化を示し都市温暖化の影響を強く受けた観測点だったとしています。
上記の図1には、NOAAによるもう一つ重要な操作が含まれていました。
世界平均気温は、地表面を緯度5度、経度5度で分割した格子を単位として計算します。そして、格子内に存在する観測点データから格子内の平均温度を計算し、それを格子面積で重み付けして加重平均するのです。
格子数は世界全体で約8000となり、地上面積が約30%なので、地上の格子点数は2400程度になります。因みに、緯度5度、経度5度の範囲は、日本では青森から兵庫あたりまでの、本州の大部分が含まれる広さです。
GHCNでは、採用観測点を1500程度までに減らした結果、格子内に一つも採用観測点が存在しない格子が出現しました。ワッツ達は、その数は1026になるとしています。
つまり、地上の格子区分の内の40%強において、採用観測点が一つも存在しない異常な状況になったのです。では、これにどう対処したのでしょうか。
NASAは、かねてから、1200kmルールという考え方を採用していました。これは、1200km以内なら、他の地点の気温データで代替できるという考え方です。
NOAAもCRUも同じ考え方を適用していたようです。しかしながら、1200kmも離れた地点のデータで代替可能という根拠は何かあったのでしょうか。
そして、上記の図1は、データのない格子点に、この1200kmルールによって、遠隔地の気温データがコピーして適用されたのです。ワッツ達によれば、大抵の場合、20世紀の後半において、主に、都市化により高い温度上昇を示していた地点の気温データで代替されたようです。
つまりこうゆうことです。IPCCは、“20世紀の後半、特に、1990年以降において世界気温は異常に上昇した”としていましたが、その気温データの基礎になっていたNOAAのGHCNは、採用観測点の間引きと高温地点データによる代替適用によって“人為的温暖化”を示していた、という可能性が高まったのでした。
今、NOAAのGHCNでは、これまでに説明したことに加えて様々な温度データの操作があったのでないか、と疑われています。次回以降では、そうした事例を説明します。
|
2010年11月11日(木)
前回および前々回では、米国および日本の気温観測点の環境状況について説明し、気象観測にかかる先進国の両国においてさえ、測定環境が悪化していることを書きました。
今回からは、数回に分けて、日本では、メディアが報道しない故にあまり知られていない世界気温データの実態を紹介してゆきます。
世界気温データは、米国商務省傘下の海洋大気圏局(NOAA)の下部組織である国立気候データセンター(NCDC)と、英国気象庁のハドレー気候センター(Hadley
Centre)が世界各国からデータ収集し、米国航空宇宙局(NASA)のゴダード宇宙研究所(GISS)、英国イーストアングリア大学(UEA)の気候研究所(CRU)が解析して公表してきました。
そして、これまで、世界には三つの独立した世界気温データがある、とされていました。
1)NCDCが管理する、GHCN(The Global Historical Climatology Network)
2)NASAのGISSが管理する、GISTEMP
3)UEAのCRUが管理する、CRUTEMP
2009年11月17日に「クライメートゲート事件」が発生した直後、“世界気温データはおかしいのでは”という批判、指摘に対して、多くの人が、“(上記の)三つのデータソースが、同じ傾向を示しているので、データはおかしくないのでは”とコメントしていました。
しかしながら、その後、世界気温データの“元締め”はNOAAのNCDCであり、NASAのGISSも、UEAのCRUも、使用元データの大半をNCDCに依存しており、必要に応じて、修正や補正をしていたことが判りました。
三つの世界気温データは、元データが同じだから同じ傾向になるのは“当然”だったとも言えます。
世界気温データに関しては、「クライメートゲート事件」が発生する前から、問題ありとの指摘がされていました。そして、事件で公開された交信電子メールには、上記の三つの組織の科学者達が登場していました。
事件後の時間経過とともに、世界地上気温データなるものが、とんでもなくひどい実態だったことが、次から次と暴露されてきたのです。
「MUSINGS FROM THE CHIEFIO」というHPを運営しているE.M.Smithという人がいます。
Smith氏は、NOAAのGHCNについて、気温算出に用いる観測点(以下、採用観測点と呼ぶことにします)の数と世界気温データ推移の関係を調査して報告しました*。
*http://chiefio.worldpress.com/2009/11/03/ghcn-the-global-analysis/・
Smith氏の報告によれば、採用観測点数は、下図1の青線のように、1980年には約6000基あったのが、現在では1500基以下まで低下したのです。第一段階は1990年頃の急速な減少、第二段階は2005年以降での更なる減少でした。
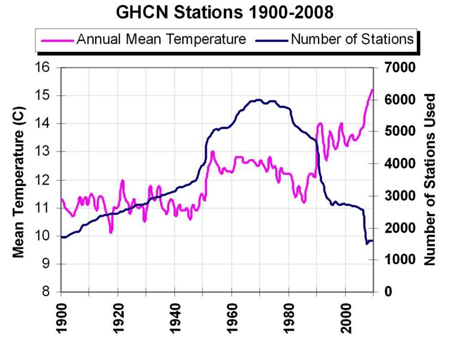 図1 GHCNにおける世界平均気温(赤)と採用観測点数(青)の推移 図1 GHCNにおける世界平均気温(赤)と採用観測点数(青)の推移 |
現在、主な国および地域の採用観測点数は、概略、以下のようになっているようです。
米国(130)、ロシア(90)、中国(70)、日本(38)、欧州(320)、カナダ(30)南米(170)、アフリカ(250)、インド(35)、豪州&ニュージーランド(70)
そして、採用観測点数の減少(間引き)に反比例するかのように、平均気温(赤線)は1990年頃から急激に上昇した後、2005年過ぎから再度、上昇していたのです。間引きと気温変化の間には見事なまでの相関があるように見えます。
次回以降で、この中身について、説明します。
|
2010年11月8日(月)
前回では米国の気温観測点の環境について説明しました。では、日本はどうなっているのでしょうか。
東北大学名誉教授で気象学権威の近藤純正先生は、自ら、気象庁の気象台や測候所の環境調査を実施し、検証されてきました。そして、検証結果はご自身のHP*でレポートとして公開されておられます。(*http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/)
レポートには、気象観測について貴重なデータが掲載され、重要な示唆が含まれているように思います。近藤先生は、また、日本の気象観測の環境劣化が深刻な問題だと警鐘を鳴らして来られましたが、日本の主要メディアが報じたことは一度もないのではないかと思います。
全国170箇所の観測点の状況を詳しく調査された結果、日本の状況は米国ほどひどくはないようですが、同様のことが生じているらしいのです。
観測点周辺において、樹木の成長・繁茂、建物の建設が進み、通風が低下して、測定温度は上昇しているのです。近藤先生は、これを“日だまり効果”と命名されています。
近藤先生は、正確な気温測定には日だまり効果が0.1℃以内であることが不可欠、と書かれていますが、全国170箇所の観測点の内、この条件にあてはまるのは、寿都、根室、浦河、室蘭、深浦、宮古、金華山、室戸、屋久島の9ケ所だけだったようなのです。
日だまり効果は年を追って拡大し、2000年までに、多くの測定点で0.2℃〜0.6℃程度上昇した と解析されました。一例を示しますが、この例では、1960年〜2000年の間で、日だまり効果は、0.6℃になっています。
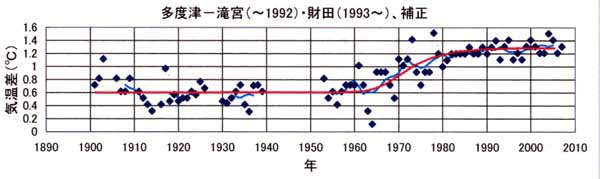 図1 多度津における日だまり効果(近傍観測点との差異) 図1 多度津における日だまり効果(近傍観測点との差異) |
ひだまり効果の変化は、都市化と密接に関連していると思えます。
気象庁HPには、都市化の影響が比較的少ない全国17か所*の観測点の平均値を用いて年平均温度を算出する、と記されています。
そして、この100年間の平均温度上昇は1.1℃だったとしています。
*網走、根室、寿都、石巻、山形、銚子、水戸、長野、飯田、伏木、彦根、
境、浜田、多度津、宮崎、名瀬、石垣島
しかしながら、この17ケ所の中でも、日だまり効果が0.1℃以内の観測地点は、根室、寿都の2地点のみだったようです。また、17箇所の多くは、日だまり効果のみならず都市化が原因でも温度上昇している、とされました。
欧州やその他の国に関して、こうした体系的な調査・解析事例があるのか判りません。しかしながら、筆者は、もし調査すれば類似の結果が出るに違いないと考えます。観測点周辺環境悪化は、結局の所は都市化が原因であり、都市化の進展状況は国によってあまり変わらないと思えるからです。
前回に紹介したワッツ達の調査によれば、最近では、世界各国で空港内に設置した気温観測点の割合が増加しているらしく、豪州やニュージーランドでは、今や、観測点の実に70%以上が、空港内設置になっているようです。
空港内は、通風環境は良いかもしれません。他方で、至るところがアスファルト舗装されていて、航空機による排ガスの影響も考えられます。従って、一般論としては、空港内は良好な測定環境とは言いがたいでしょう。表示温度は上がり易くなっている可能性があります。空港内設置が増加しているのは、管理が容易になる側面があるのでしょうが、主な目的が気候変動監視でなく航空管制にあることによるようなのです。
結局、気温観測については、結構、ぞんざいに扱われているように思えます。気温観測にかかる実態は、中味を知れば実にお粗末 という話が多いということでしょうか。
|
2010年11月4日(木)
小学校の頃、理科の教科書に百葉箱の話が出ていたことを思いだします。地上気温を測定する時、温度計の周辺環境によって指示値が変わりやすく、地上気温の正確な測定は、結構、大変なのだと感じたものでした。
観測点周辺の環境については、いろいろと制約条件が決められてきました。たとえば、周囲30m位は、建物や木など通風の妨害物がなく、排熱装置や機器が存在しないこと、地面は芝生のような丈の小さい草地であること、等など。
米国気象予報士でTVでも活躍してきたワッツ(Anthony Watts)という人がいます。ワッツ達は、海洋大気圏局(NOAA)の下部組織国立気候データセンター(NCDC)が管理するUSHCN (US Historical Climatology Network) という米国気温データネットワークに関して、2004年頃から、気温観測点の環境状況の実態調査を続けて、自身のブログWUWT(Waats Up With That?)*上で観測点の現地写真を公開してきました。
* http://waatsupwiththat.com-Waats Up With That?
全体で1200箇所程度ある観測点の内、約1000箇所を調べ解析したところ、驚くべき結果がわかったのです。気温観測点の大半が、熱源の近辺、屋上、建物の傍、風通しが悪い場所、アスファルト舗装の近辺、空港内、廃棄物処理場近辺 等々 劣悪環境下にあったのです。大半の温度計の読みが自然と高温になる場所にあったのです。
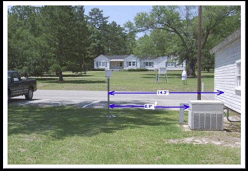
図1 事例1 |

図2 事例2 |
そして、下図に示すように、観測点の実に87%が、NOAA自身の基準で、測定温度が、正常より1℃以上も高めに出る劣悪観測点であるとわかったのです。
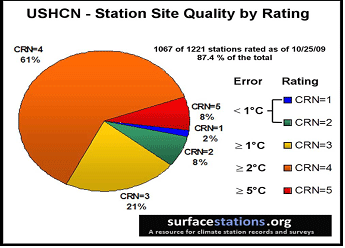
図3 USHCNの観測点環境調査 |
CO2温暖化論の推進者として著名なアル・ゴア氏は、著書「不都合な真実」の中で次ぎのように書いています。
『温暖化を否定したがる人は、科学者が実際に観測していることをヒートアイランド効果に過ぎないと主張する。・これは全くの間違いである。気温測定は、通常、公園で行われている。公園は、基本的に、ヒートアイランドの中では涼しい所なのだ。』
しかしながら、お膝元の米国の気温観測点の状況は、ゴア氏の説明とは“似ても似つかぬ実態”だったということでした。
周辺環境が自然に悪化した地点に加えて、自動化による連続測定化やデータの遠隔送信の必要性などから、管理の容易な都合のいい場所(そして悪環境の場所)に移設されたものも多いのでしょう。NOAAは、こんな実態を知らなかったのでしょうか、それとも、何らかの意図があって、あえて、放置してきたのでしょうか。
地球温度は、この100年間で0.7℃上がったと騒がれてきました。そんな数字を決める測定精度が1℃を越えるというのは、論外な話 と言えるでしょう。
ワッツの仲間でカナダの気候科学者Joseph D‘Aleoという人は、“米国の地表温度の数字は、測定環境悪化の原因だけで30〜50%高めになっている”と推算しています。
|
2010年11月1日(月)
2010年、日本の夏は大変に暑かった。TVで気象庁担当官が「我々は、普通、“異常な”という言葉は使わないのですが、今年は、まさに、“異常”と言えるかも知れません。」というコメントをしていました。“CO2が増加して地球温暖化がますます進行している証拠”と思った日本人も多かったと推測します。
しかしながら、アマノジャクな筆者にとっては、こうした見方についても“ほんとうなの?”と思ってしまうのです。今や、世界中に広がり、日本人の90%以上が信じているとされる「CO2温暖化論」。その裏話を、これから、縷々、紹介してゆきます。
気象庁HPでは、「地球温暖化の原因」について以下の説明がされています。
『20世紀後半以降に見られる地球規模の気温の上昇、すなわち現在問題となっている地球温暖化の主な原因は、人間活動による温室効果ガスの増加であることがほぼ確実であると考えられています。
大気中に含まれる二酸化炭素などの温室効果ガスには、海や陸などの地球の表面から地球の外に向かう熱を大気に蓄積し、再び地球の表面に戻す性質(温室効果)があります。
18世紀半ばの産業革命の開始以降、人間活動による化石燃料の使用や森林の減少などにより、大気中の温室効果ガスの濃度は急激に増加しました。
この急激に増加した温室効果ガスにより、大気の温室効果が強まったことが、地球温暖化の原因と考えられています。』(下線は筆者)
こうした見解は、国連の下部組織「気候変動にかかる政府間パネル:IPCC」によって、世に広められました。そして、2007年に出されたIPCC第四次報告書において、19世紀の終わりから21世紀にかけての世界平均の気温は、図1のようであったとされました。(ここでは四つのデータが比較されている)。
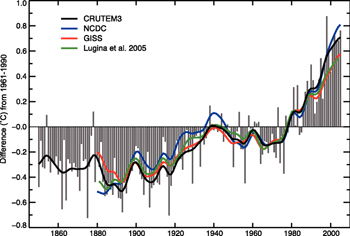
図1 IPCC報告書にある世界平均気温の推移 |
ここで、素朴な疑問が生じます。
こうした世界平均気温とはどのようにして求められているのだろうか。この結果は、本当の世界の姿を的確に反映しているのだろうか。
世界平均というからには、世界中のあらゆる場所・地域の気温データがカバーされていなければならないはず。だが、地球上には、極圏などの寒い地域、砂漠、高山など、人が住まない広大な面積がある。こんな所のデータはどうなっているのだろうか。
また、世界中に、こうした長期にわたる気温測定データがそろっていたのだろうか。先進国ならいざ知らず、発展途上国データはどうだろうか。
2009年11月17日、世界に激震を与える事件が起きました。
IPCCのCO2温暖化論の中心研究拠点、英国イーストアングリア大学の気候研究所
(CRU)のコンピュータから、フィル・ジョーンズ所長を含むIPCCのリーダー科学者達の1000通を超える交信メールと多量の文書が引き出され、米国のブログサイトに掲載されるという事件が勃発したのです。
流出情報は、科学者達が自分たちの主張を“正当化”するために「気候データの恣意的加工、改ざんや秘匿、論文誌への圧力による反対派論文の掲載妨害、等々、数々の不正行為をやっていた」という衝撃的内容を示していました。
後にクライメートゲート事件と命名されたこの事件を契機に、CO2温暖化論を巡る環境は急速に変わり始めました。そして、世界気温データについても、数々の疑問・疑惑が噴出し始めたのです。
今日からしばらくの間、世界気温データにまつわる話を紹介してゆきます。
|
 |
| Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights
Reserved. |
|